6 基本概念の転換
6-1 住居法と住宅監視制度
わが国では住宅がどのように不良化しても、住宅の将来を所有者の判断に委ねる仕組みになっています。このため道内市町村の空き家が廃屋と化して積雪で倒壊し、行政も対策を講じることができず近隣の住人に迷惑をかける事態が生じています。
木造戸建て・長屋建て・木賃アパートが中心であった時代は、特段に行政の介入がなくても終末処理は可能でした。しかし、非木造・共同・高層・区分所有・大規模になると、個人や企業のみで終末処理を行うことは困難になります。現在は非木造共同住宅が都市住宅の中核になりつつあり、今後終末処理が社会的課題となる可能性が高まっています。
日本には建設の法律があっても居住の法律がないので、住居法制定と住宅監視制度を設けるべきです。障がい者などが地域で普通の生活を営むことを当然とする福祉の基本的な考え方も計画段階で含めた居住の最低基準を設け、不良化した住居を所有者が改善できない場合は、改善勧告や閉鎖命令などができる仕組みが必要です。現在はこれがないため、建築の自由が将来都市の不自由になる恐れが高まっています。
トップへ戻る
6-2 自転車利用の促進
パリ市の人口は217万人で面積は105.4平方km、人口密度は20.348人/平方kmで高層住宅を建てません。札幌市の人口は190万人で人口密度は1,693人/平方km、人口密度最高の白石区で5,887人/平方kmです。パリの人口密度にすれば札幌市は中央区ふたつで充分といえます。
パリでは2007年9月から自転車乗り放題の貸し出し方式を始めました。駐輪場は市内に1,451ヶ所26千台分を確保し、30分以内の利用に限定して駐輪場から駐輪場へつなげば何回でも利用できる方式です。年間契約は29ユーロ(4千円)で1日の契約は1ユーロ、7日の契約は5ユーロときわめて安上がりです。
中心市街地で居住者が激減する理由は駐車場不足が大きな原因です。中心となる市街地に居住者を定着させるために、先進国では様々な自転車への取り組みが行われています。自転車の利用を促進して電動自転車を利用できれば距離も伸びます。雨・風・交通安全・駐輪・専用自転車道路対策ができれば効果が上がります。
トップへ戻る
6-3 できることから
我が国の都市計画は最小限の規制で自由な開発を承認しているため、都市計画と住宅政策は一体化せず都市は私空間の集合となって公共空間としての統合性がありません。自己主張する建物が連続して都市としての景観統一が忘れられ、全国の街を醜悪な風景にしてしまいました。
車に頼らない街づくりはヨーロッパの先進国では当たり前の目標になりつつあります。都市の拡大は無駄な行政コストを膨らませ、民生・福祉・教育費を圧迫していることから日本もコンパクトシティ化を目指すことが最善でしょう。
イギリスではサッチャー政権が地方分権を推進し、地方行政はさらに住民に多くの権限をゆだねました。街づくりは「住民参加」ではなく「住民主体」が強調され、公共住宅の修繕事業や入退去業務も住民組織にゆだねられました。不良住宅地区の改善事業なども、最初に行政が行う作業はマスタープランづくりではなく住民の輪をつくることでした。
住民は最初から知識や経験があるわけではないので、手分けして様々な調査や分析を行いながら学習を重ねていきます。定年退職した多数の公務員が住民のワークショップに加わり、NPO団体や専門家を招いて講演を依頼する場合も多く、これらの必要経費は行政が負担しています。
老人や子ども、外国人などが当たり前のことのように参加し、計画を練っていく過程が地域再生となります。住民がプランを完成したときには、住民同士が顔見知りになるだけではなく多様な人間関係が築かれています。
東京都三鷹市は、市民主体の街づくりNPOが毎年市長に公開の場で街づくりの提言をしています。勉強のために講演会を何度も開催していますが、その費用は三鷹市が負担しています。会場の設定や聴講者募集、受付や運営などのすべては市民が行い、提言内容が実現した事例も増加しています。
三鷹市のようにできない地域がほとんどですし、町内会やマンション管理組合の活動は役員や理事が代われば継続性が途切れるという弱点があります。理想を夢見て待つのではなく、問題意識を共有できる高齢者が声を掛け合い、互いに助け合えるよう交流の機会を設けることから始めましょう。
謝辞:文中に掲載した写真は、プロジェクターで投影されたものを撮影して転載しました。ありがとうございます。
トップへ戻る

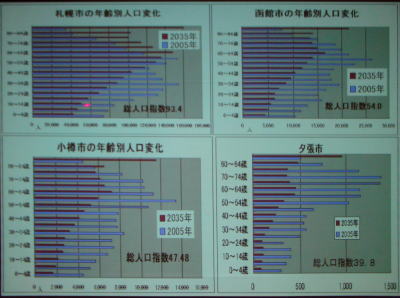
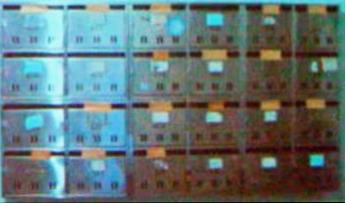 地域の空き家や空き住宅、空き店舗や空ビルが増加し、大型店舗の倒産と競売不調などで中心市街地はゴーストタウン化してゆきます。現在の群馬県では、マンション併設の店舗や事務所の半数は空き室となり、面積では八割が使われていない状態です。(メールボックスを見ると、居住者がほとんどがいないと訴えています。)
地域の空き家や空き住宅、空き店舗や空ビルが増加し、大型店舗の倒産と競売不調などで中心市街地はゴーストタウン化してゆきます。現在の群馬県では、マンション併設の店舗や事務所の半数は空き室となり、面積では八割が使われていない状態です。(メールボックスを見ると、居住者がほとんどがいないと訴えています。)