1 災害とは
地震や台風は、実は単なる自然現象です。人的や物的な被害が発生すると災害になります。人が住んでいるから災害になるのです。日本は「災害列島・地震大国」と言われるような自然現象が多いので、災害にならないように自然現象と付き合う「すべ」が必要になります。これを「防災・減災」といいます。
・ 有珠山噴火のとき
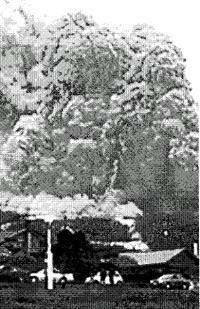 ① 2000(平成12)年3月27日
① 2000(平成12)年3月27日
・ 火山性地震発生。北大観測所が数日以内の噴火を
示唆。
ア. 2000(平成12)年3月29日
・ 気象庁が通常は噴火後に出す「緊急火山情報(当
時)」を発表。
・ 壮瞥・虻田・伊達の三市町は避難勧告と勧告指示
をだして住民は避難を開始。
イ. 2000(平成12)年3月31日の13時10分頃、
有珠山が噴火。
・ 人的被害(死傷者)はゼロでした。
2 地域災害の実態
何が起きて、どのようにして命を守った(減災)か。災害から学んだ教訓は何かを考えます。
2-1 関東大震災の教訓
1923(大正12)年9月1日11時58分に発生、M7.9、最大深度6。
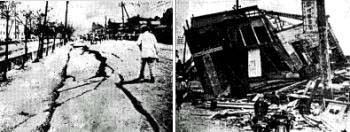 右の写真は、東京の赤坂と牛込の様子です。
右の写真は、東京の赤坂と牛込の様子です。
関東大震災で9割の方々が焼死しました。この経験が「地震だ!火を消せ!」という合言葉になりましたが、現在は修正されています。
昭和35年に関東大震災が発生した9月1日が「防災の日」と定められました。
2-2 阪神・淡路大震災の教訓
1995(平成7)年1月17日5時46分に発生、M7.3、最大深度7。全壊家屋104,906棟、半壊家屋144,274棟。この経験から、住居の「耐震化を急げ」が合言葉になりました。

火災発生件数285件、全焼家屋7、036棟、電気関係による火災139件中85件は通電火災。

火災発生件数のうち6割が通電火災といわれています。停電後に電気が復旧すると、スイッチガ切られていない電気製品が過熱して出火する危険性があります。避難するときはブレーカーを遮断することで通電火災を防ぐことができます。避難する時は「ブレーカーの遮断」が合言葉になりました。

阪神・淡路大震災の死者6,434人のうち、9割の方々は瞬間圧死でした。この経験から、住居の「家具の固定が命を救う」が合言葉になりました。

平成18年に阪神・淡路大震災が発生した1月17日が「防災とボランテイアの日」と定められました。掲載した12枚のカラー写真は、神戸市市民参画推進局広報課制作の「神戸市1.17震災写真オープンデータ」より転載しました。ありがとうございます。
2-3 東日本大震災の教訓
2011(平成23)年3月11日14時46分に発生、M9.0、最大深度7。震源域は、岩手県沖から茨城県沖までの南北約500km、東西約200kmのおよそ10万km2という広範囲と推定されます。
この地震により、場所によっては波高10m以上、最大遡上高40.1mにも上る巨大な津波が襲来し、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害が発生しました。死者の90.6%(14,308体)は水死で、圧死・損傷死・その他の死者は4.23%(667体)、焼死者は0.92%(145体)、不詳は4.22%(666体)となっています。

東日本大震災では避難所の不衛生や寒さなどが原因で、避難後に死亡する(震災関連死)高齢者が相次ぎました。2013年12月17日の毎日新聞は、「福島県内の震災関連死による死者数が地震や津波による直接死者数を上回った」と報じました。震災関連死は60歳以上の高齢者に多く2,841人にも上りました。
内閣府は、東日本大震災の教訓として、「被害を最小化する「減災」に取り組み、大規模災害にも負けない「ゆるぎない日本」を構築して、次世代に引き継いでいくことは我々の世代が果たさなければならない歴史的な使命である」としています。
掲載した写真は LINE Corporation「東日本大震災の衝撃画像集」より転載しました。ありがとうございます。
2-4 日本が教訓としたこと
国土交通省東北整備局東北圏地方計画推進室の東北圏広域地方計画協議会は、東日本大震災教訓集「広域大災害に備え~国民の安全・安心の確保に向けて準備すべき29の要点」をまとめました。以下の文章は、東日本大震災教訓集からの引用です。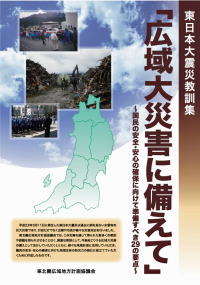
平成23年3月11日に発生した東日本大震災は過去に例を見ない未曾有の巨大災害であり、行政だけでなく企業や市民が様々な災害対応を行いました。東北圏広域地方計画協議会では、この災害を通じて得られた数多くの教訓や課題を埋もれさせることなく、貴重な教訓として、今後起こりうる広域災害の備えとして生かしていただくとともに、様々な地域計画に活用していただき、国民の安全・安心の確保に向けた地域全体の防災力の強化に役立てていただくために作成したものです。
・ 発災・初動対応
ア. 発災直後の情報収集
大規模災害時は、早急に広域な被災状況を正確に把握することが、その後の体制を
構築する上で重要。
イ. 広域交通基盤の啓開
大規模災害時には、人命救助・物資輸送のためのルート確保等に向けた人材・機材
の結集が必要。
ウ. 初動対応期の自治体支援(リエゾン)
大規模災害時において、リエゾン(災害対策現地情報連絡員)派遣などによる情報
収集が自治体支援に有効。
エ. 衝動対応期の自治体支援(災害直後の通信確保)
大規模災害時に通信が途絶した自治体においては、衛星携帯通信や専用回線(無
線)が有効。
オ. 初動対応期の自治体支援(専門技術者派遣)
大規模災害時において、被災自治体の専門技術者などの派遣による的確かつ迅速な
復旧への対応が有効。
カ. 初期対応期の自治体支援(支援物資調達)
大規模災害時において、救援物資調達などの組織の垣根を超えた総合的な取り組み
が有効。
・ 応急復旧・被災地応急対応期
ア. 広域交通基盤の緊急復旧
応急復旧に備えた資機材の速やかな工事契約による迅速な応急復旧が重要。
イ. 広域的な地域間の連携・支援・機能分担
圏域を超えた支援体制の構築や、国や地方の役割の明確化等による災害時における
連携体制の確立が必要。
ウ. 多様な階層・機関による連携・支援
災害時における多様な階層による地域間連携が必要。
エ. 被災地の再生・被災者の生活支援
災害時における避難所のニーズの把握、共有化などによるきめ細かな被災者支援体
制の構築が必要。
オ. 多様な主体による取組
「新しい公共」など、多様な主体が主導する被災地域の復興の促進が必要。
・ 復興期
ア.広域交通ネットワーク
東北全体のネットワークを考慮した代替性(リダンダンシー)の確保が必要。
イ. 災害に強いまちづくり
「被災」の考え方に基づく多重防御による「津波防災まちづくり」の推進が必要。
ウ. 災害への備え
様々な被害絵の応急対応や広域的対応等、平時からの実践的な防災訓練、防災教育
が必要。
エ. 農林水産業
農林水産業の復興に資する早期の経営合理化等の体質強化が必要。
オ. 自然災害・景観・生活環境・地域コミュニティ
復興にあたって自然環境への配慮や、地域文化の復興、地域コミュニティの再生、
被災者の孤立に対する支援が必要。
カ. 大規模災害時の災害廃棄物の効率的な処理
津波など大規模災害時に災害廃棄物の効率的な処理。
以上が東日本大震災教訓集からの引用です。
3 実際にあった事例
3-1 先人の教えが人々を救う
岩手県宮古市姉吉の海抜約60メートルのところに「大津波記念碑」が建っています。1933年(昭和8年)3月3日午前2時30分に発生した昭和三陸大津波の惨劇と、津波被害者が戒めを記したものでした。
碑には次のように記されています。上段は「碑文」、下段は「はげちゃん訳」です。
高き住居は児孫の和楽 想へ惨禍の大津浪 此処より下に家を建てるな 明治二十九年にも 昭和八年にも津浪は此処まで来て部落は全滅し 生存者僅かに前に二人後に四人のみ 幾歳経るとも要心何従
高い位置に住んでいれば子どもや孫も安全に暮らせる。大津波の惨劇を思い出し、この記念碑より下に家を建てるな。明治29年と昭和8年に大津波が襲来し、部落は全滅して助かったのはわずか4名だった。何年たってもこれを忘れてはならない。
岩手県宮古市の沿岸部は津波にのみこまれましたが、先人の教えを守った重茂半島の姉吉地区(12世帯約40人)は全ての家屋が被害を免れ、犠牲者は1人も出なかったのです。
3-2 保育園児、奇跡の脱出
岩手県・宮城県・福島県の被災保育所は315ヶ所で、28ヶ所は津波で流されました。日頃の避難訓練ととっさの判断で高台へ逃げたことが効を奏し、保育園児と職員の人的被害はわずかでした。
3-3 間に合った非常避難通路
岩手県大船渡市越喜来小学校は海から200mの位置にありました。津浪襲来時に2階から1階へ下りて遠回りするこれまでの避難方法では間に合わないとし、校長と平田市議は非常避難通路の設置を市に強く要望しました。
学校の2階から直接高台へ避難できる非常避難通路は、震災のわずか三か月前の2010年12月に完成したばかりでした。児童71名と職員はこの通路から高台へ避難して全員無事でした。
3-4 校長の的確な判断
宮城県南三陸町立戸倉小学校はいつもの訓練で4階建ての校舎屋上へ避難していました。校長は地震の揺れの大きさと長さから「想定外の津波」を意識し、国道を横断する危険性を冒してまで高台への避難を決断しました。全員避難を完了した20分後、校舎は津波に飲み込まれました。
3-5 津波てんでんこ
釜石市の小中学校では2005年から専門家を招いて防災教育を実施していました。「津波の時には親子であってもかまうな。一人ひとりがてんでんばらばら(てんでんこ)に高台へ逃げろ」と教えられていました。
釜石市では1,000人以上が津波の犠牲になりました。小中学生の半数は津波に襲われた区域に居住していましたが、小中学生のほとんど約2,900人は避難して無事でした。
3-6 特養老人ホームの奇跡
宮城県岩沼市の赤井江マリンホームは、海から200mの位置にある特別養護老人ホームで、入所者のほとんどは車椅子で介護の必要性の高い人たちが大半でした。海側にある防波堤は6.5mのため避難すべきか迷っていると、高さ10mの津波襲来を告げるラジオのニュースですぐに避難を決断しました。
指定避難先の仙台空港ターミナルへ特養老人ホームや職員の車9台でピストン輸送を開始し、利用者96人を含む144人の避難完了後、津波は赤井江マリンホームを飲み込みました。的確な判断は一人の犠牲者も出さなかったのです。
3-7 死傷者ゼロの町
岩手県の最北、南北に細長い洋野町には19千人が住んでいます。明治29年の三陸大津波で254人の犠牲者をだし、昭和8年の三陸大津波では107人の犠牲者をだしました。
東日本大震災発生から50分後、高さ10mの大津波が洋野町を襲いました。家屋の全半壊180棟、漁船も7割が被害を被りました。しかし、住民はもちろん消防団員や職員の死傷者はゼロでした。
消防団員は住民の避難誘導にあたるとともに、重要任務である水門閉鎖を12分で完了して高台へ避難しました。家を出遅れた住民は、消防団員の避難する姿を見て我先にと高台へ逃げました。
2006年から洋野町消防署が中心となって行った防災訓練等の見直しが効を奏した結果でした。昭和三陸大津波の来襲日に合わせて実施していた防災訓練を日曜日の日中に変更し、消防団員の潮位監視や水門閉鎖後の警戒を廃止して任務完了後は全員避難、高台へ避難後は低地へ続く道路を封鎖しました。
2010年2月28日のチリ地震津波来襲時に、全26基の水門閉鎖に29分かかりました。この教訓から、閉鎖しても支障のない水門を常時閉鎖して緊急時閉鎖水門数を9基に減少させました。自主防災組織は高台へ上る避難路の除草や整備し、過去の大津波経験者を語り部として住民への啓発活動を行っていました。
4 災害に備えるとは
ア. 現実に「何が起きる・起きそう」であるかを知り(予測し)
イ. その「予防策」と、それが起きた場合の「被害最少化策」を考え
ウ. それを「実行」すること(みんなで!)
自助・・・家庭で 共助・・・隣近所・職場で
この考え方はすべての危機管理に共通します。これを邪魔する人間の心を「正常化の偏見」といいます。
4-1 正常化の偏見
災害に対する人間の基本的な心理は、現実に起きる事・起きそうなことを見ようとしない「正常化の偏見」であり、防災を進めるためには「正常化の偏見」の排除が必要です。
ア. 事態を楽観視し、災害を軽視する
たいしたことではない、と勝手に思い込む。
イ. 自分に都合よく考える
自分だけは絶対に死なない、と思い込む。
ウ. 客観的な予想ではなく、願望も含め執着する
そうなってほしい、という気持ちにこだわる。
4-2 想定と想定外
良く使われる「想定」と「想定外」の意味を覚えて正しく使いましょう。東日本大震災の教訓から「想定外をなくす」ための見直しが必要とされています。
ア. 想定内 想定できたし、だから対策も取っていた。
イ. 想定外
ア. 人知を超えた「想定外」(本当にまったく想定できなかった)
イ. 想定はできたが、対策をとる範囲には含めなかった「想定外」(なぜ対策の
対象としなかったのか)
a. 想定できてもそれに対して打つ手がない(想定の取りようがない・・・
例:隕石衝突)
b. 想定はできたが発生確率は極めて低く、その対策には莫大な費用がかか
る(だから想定から外した・想定しないことにした)
4-3 日本列島の現実
日本の陸地面積は世界のたった0.25%(1/400)です。世界で起きる地震の10%は日本で発生し、世界で起きるM6以上(中規模以上)の地震の23%が日本で起きています。火山も10%が集中しています。ですから、日本は地震大国であり温泉大国です。
4-4 札幌の活断層
札幌市の近くに「石狩低地東縁断層帯」という活断層の存在が確認されています。活断層は、最近の数十万年間に概ね千年から数万年の間隔で繰り返して活動し、その痕跡が地上にも現れ、今後も活動を繰り返すと考えられている断層です。
札幌市の直下に「活断層」は確認されていませんが、活動すると「最大深度7」が想定される「伏在活断層」の存在が推定されています。
5 地震災害に備えて
一般家庭の場合は「自助」、それから「共助」です。
5-1 地震への心構え
大切なのは「死なないこと」「怪我をしないこと」です。地震が来ても、怪我をしない環境をつくっておきましょう。
ア. 自宅の耐震化は大丈夫ですか(必要により耐震診断を受ける)。
イ. 家具などの固定は大丈夫ですか(できるだけ倒れやすいものは置かない)。
ウ. 落下防止は大丈夫ですか(高いところにものは置かない)。
エ. 情報機器は固定していますか(パソコン、テレビなど)。
5-2 揺れを感じる前に
ア. 緊急地震速報(テレビやラジオ、携帯電話から流れる
あわてずに、安全なところへ移動する。
※ 近くで起きる地震は、緊急地震速報が間に合わないことに注意。
イ. ゆれている最中はとにかく身を守る
机の下に入る、座布団で頭を守る、窓や家具から離れる、高層住宅の場合はでき
るだけ廊下へ逃げる。
5-3 揺れが治まったら
ア. 火を消す。
イ. 戸や窓を開けて出口の確保。
ウ. 家族の安全確認。
エ. 隣近所の助け合い・・・消火・救助・けがの手当て・安否確認。
5-4 インフラの停止
地震によりインフラストラクチャー(インフラ)が停止して、電気・ガス・水道が止まりました。固定電話も携帯電話も通じません。道路は寸断され、動いている車を見かけません。
ア. 余震が不安と判断。
避難場所へ避難(どこへ? なにを持って?)
イ. 余震が来ても支障ないと判断。
自宅で生活を継続(でも、電気・ガス・水道は使えません)。
a. 食事はどうする(非常用食料、携帯ガスコンロ・・・・)
b. 水はどうする(ペットボトルなどで非常備蓄・・・)
c. 暖房をどうする(移動式灯油ストーブ、プロパンガスストーブ・・・)
d. トイレはどうする(簡易トイレ、風呂水で貯水確保・・・)
e. 照明はどうする(懐中電灯、ローソク、ランタン・・・)
f. 情報がほしい(携帯ラジオ、車のラジオやテレビ・・・)
ウ. その他の対策
a. 家族で避難場所を確認、落ち合う場所を確認
b. 家族で連絡方法を確認(非常用伝言ダイヤルなど・・・)
c. 講座坂東・保険証番号・年金番号・処方薬・電話番号などのメモ
6 洪水災害に備えて
6-1 洪水が迫った
常日頃、洪水ハザードマップで確認しておきましょう。
ア. 自宅はどのくらいの雨が降ったら、どのくらい浸水するのか。
自宅が傾斜地等の近くにある場合は土砂災害にも注意。
イ. どのような状態になったら避難が必要か
避難のタイミング。
ウ. 避難場所はどこか。
エ. どこを通って避難するか
避難経路、普段通れる場所が浸水により通れなくなることに注意。
オ. 何を持って避難するか
非常持出品 ⇒ 普段から準備
6-2 台風・大雨が迫った
ア. 正確な情報取集
イ. 早めの自主避難
浸水後の避難は非常に危険。
ウ. 避難の呼びかけに注意
エ. 避難する場合は2人以上
動きやすい服装で。
オ. お年寄りや障がいのある方の避難衣協力
6-3 気象は大きく変動する
降ったことのない雨が降れば、起きたことがないことが起きます。
6-4 一番大切なこと
災害に備えるとは、助かる「すべ」を知りことです。自然災害はいつどこで起きてもおかしくありませんし、気象災害はその前兆をとらえることができます。
一番大切なのは、どうしたらよいかをみんなで一緒に考えて実行することです。災害列島日本から防災大国日本へ変えることです。