1 消防団とは
消防団は、「自分たちの町は自分たちで守る」という郷土愛と奉仕の精神から生まれたもので、地域住民の中にあっては防災のリーダーとしての役割を果たします。消防本部や消防署と同様、消防組織法に基づいて各市町村に設置されている消防機関です。
消防団は、消防署と同じく市町村に設置されている消防機関です。消防署は、機動力・即時対応力のある常備の消防機関であるのに対して、消防団は、動員力・地域密着性のある非常備の消防機関であり、お互いに協力しながら活動しています。
消防団員は、自営業・会社員・主婦・学生などの本業を持っている人々が、特別職の地方公務員(地方団体の長・議会の議長・非常勤消防団員など)として活動しています。近年は女性の消防団員も増加し、一人暮らし高齢者宅への防火訪問、応急手当の普及指導などに活躍しています。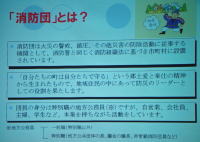
消防団員に採用される区域に居住している人、または勤務・通学されている方で、18歳以上の心身ともに健康な方であれば応募できます。詳しくは、勤務または通学されている地区の消防署にお問い合わせください。
2 消防団の歴史
消防団は、江戸時代に八代将軍吉宗が南町奉行の大岡越前守に命じ、町組織としての火消組を編成替えして町火消「いろは四八組」を設置させたことが始まりと言われます。各火消組に「いろは」等の名前を付けたことでお互いの名誉にかけて競い合って働くという結果が生じ、消防の発展に多大な成果を得ることとなりました。
町火消は町奉行の監督下にありましたが、純然たる自治組織で経費の一切も町負担とされ、組織・人員ともに町役人の自由に委ねられていました。組員は無報酬で、費用のほとんどは器具設備等の購入に費やされました。
明治5(1872)年に消防組ができましたが全国的には公設消防組は少なく、ほとんどが名前だけというものが多かったようです。明治27(1894)年に消防組規則(勅令第15号)を制定して全国的な統一を図りましたが遅々として進まず、警察署長等の積極的な働きかけなどで大正時代末には飛躍的に消防組の数が増大しました。
昭和13(1938)年に消防組と軍部がつくった防護団を統合して「警防団」としました。これにより、明治以来の消防組は解消して全国一斉に警防団が発足し、警察の補助機関として従来の水火消防業務に防空の任務を加えられて終戦に至りました。
戦後の昭和22(1947)年に従来の警防団は解消され、消防が警察から分離独立するとともに新たに全国の市町村に自主的民主的な「消防団」が組織されることとなりました。
3 札幌市内の消防団
札幌市の区ごとに消防団があり、区の消防団には地区ごとの「分団」があります。平成22年4月1日現在で定員2,150名のところ、197名少ない1,953名が属しています。
| 名称 | 区域川 | 分団数 | 定員 | 現員(不足) | 内女性(割合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央消防団 | 中央区 | 13 | 279 | 249 (-30) | 43(17.3%) |
| 北消防団 | 北区 | 11 | 298 | 279 (-19) | 28(10.0%) |
| 東消防団 | 東区 | 10 | 299 | 263 (-36) | 39(14.8%) |
| 白石消防団 | 白石区 | 7 | 210 | 196 (-14) | 40(20.4%) |
| 厚別消防団 | 厚別区 | 4 | 130 | 106 (-24) | 25(23.6%) |
| 豊平消防団 | 豊平区 | 6 | 210 | 200 (-10) | 61(30.5%) |
| 清田消防団 | 清田区 | 4 | 130 | 105 (-25) | 21(20.0%) |
| 南消防団 | 南区 | 8 | 250 | 227 (-23) | 57(25.1%) |
| 西消防団 | 西区 | 5 | 200 | 192 ( -8) | 42(21.9%) |
| 手稲消防団 | 手稲区 | 4 | 144 | 136 ( -8) | 26(19.1%) |
| 10消防団 | 72 | 2,150 | 1,953(-197) | 382(19.6%) | |
4 団員の推移
4-1 主な主な職業構成
| 区分 | 卸業/小売業 | サービス業 | 建設業 | 農業/林業 | 不動産業等 | 製造業 | 運輸/郵便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 461 | 399 | 281 | 139 | 117 | 103 | 77 |
| 20年前 | 502 | 360 | 211 | 524 | 63 | 100 | 77 |
サラリーマンは日中(勤務時間)の対応がむずかしい。
4-2 年齢構成
| 総数 | 20歳 未満 | 20歳 ~ 24歳 | 20歳 ~ 24歳 | 20歳 ~ 24歳 | 20歳 ~ 24歳 | 20歳 ~ 24歳 | 20歳 ~ 24歳 | 20歳 ~ 24歳 | 20歳 ~ 24歳 | 20歳 ~ 24歳 | 65歳 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 1,953 | 8 | 36 | 106 | 207 | 238 | 254 | 286 | 320 | 282 | 183 |
| 20年前 | 1,963 | 2 | 26 | 146 | 217 | 368 | 372 | 301 | 226 | 143 | 89 |
平均年齢は50.11歳(男性50.03歳、女性49.5歳)で、最年長者は85歳です。
5 活動の内容
5-1 災害対応
災害発生時に消防団は様々な役割を担います。災害現場での消火をはじめ、地震や風水害といった大規模災害発生時の救助・救出、警戒巡視、避難誘導、災害防御、行方不明者の捜索など様々な現場で活躍しています。
5-2 予防・警戒
高齢者宅への防火訪問、住宅用火災警報器の普及促進、自主防災組織への訓練指導、防火チラシ配布などの広報活動、地域の巡回パトロール、応急手当の指導、消火栓の除雪なども行っています。
5-3 研修・訓練
消防学校での研修、応急手当指導者の研修、消火訓練、ポンプ・各種資機材等取扱訓練など。
6 活動の状況
| 区分 | 災害対応 | 予防/警戒 | 研修/訓練 | その他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | |
| 平成17年度 | 306 | 894 | 1,767 | 10,496 | 1,912 | 17,345 | 2,945 | 13,808 |
| 平成18年度 | 291 | 854 | 1,870 | 10,050 | 1,705 | 15,712 | 3,218 | 14,199 |
| 平成19年度 | 236 | 602 | 1,812 | 15,583 | 2,058 | 10,434 | 3,258 | 13,297 |
| 平成20年度 | 234 | 674 | 2,258 | ;9,921 | 1,513 | 9,013 | 3,794 | 13,924 |
| 平成21年度 | 360 | 1,003 | 1,969 | 9,031 | 2,350 | 15,918 | 3,883 | 13,438 |
7 施設・装備等
災害に対応するための資機材(小型ポンプなど)や車両(南区と手稲区のみ消防団車両)、これらを保管するための器具置場や詰所などがあります。また、消防団活動を行うために必要な被服(征服・活動衣・防火衣)や装備品が貸与されます。
救出活動時の使用資機材には、ストライカー(携帯用コンクリート破壊器具、大型万能ハンマー)、エンジンカッター、手動式油圧カッター、チェーンソーなどがあります。
8 報酬や補償
8-1 予算と支出
| 項目 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 総予算 | 374,379,000 | 381,485,000 | 366,721,000 | |
| 内訳 | 報酬(年報酬、出勤・技術報酬) | 227,448,000 | 227,448,000 | 218,691,000 |
| 共済費 | 51,744,000 | 51,744,000 | 51,948,000 | |
| 被服、装備品、資機材等 | 21,265,000 | 22,774,000 | 22,459,000 | |
| その他 | 73,953,000 | 79,519,000 | 73,623,000 | |
平成22年度消防団予算の市民一人当たり負担額は、
366,721,000円÷1,904,903人=192.5円/年
8-2 年報酬
階級に応じて年1回支給。
| 階級 | 年報酬金額 |
|---|---|
| 団長 | 82,000 |
| 副団長 | 68,500 |
| 分団長 | 50,000 |
| 副分団長 | 45,000 |
| 部長及び班長 | 36,500 |
| 団員 | 35,500 |
8-3 出勤報酬
災害対応または訓練等の活動をした回収及び時間に応じて支給。
| 区分 | 1時間未満 | 1~3時間未満 | 3~5時間未満 | 5時間以上 |
|---|---|---|---|---|
| 水火災 | 3,200 | 4,400 | 6,800 | 7,900 |
| 警戒/訓練等 | 2,200 | 3,100 | 4,800 | 5,600 |
9 公務災害補償
消防団活動により不詳または死亡した場合に支給。
療養補償 負傷または病気になったときの療養費用。
休業補償 負傷または病気になって働けない場合の補償。
傷病補償年金 長期の療養を必要とするときの、その傷病等級に応じた年金。
障害補償年金 身体に障害が残ったときの、その等級に応じた年金または一時金。
介護費用 負傷(傷病)補償年金を受取る権利のある者が、介護を受ける状態にあ
るときは一定の介護費用が支給される。
遺族補償 遺族に対しての年金または一時金。
葬祭費用 葬祭を行う者への葬祭費用の支給。
10 消防団員の募集
白石区防災リーダー中級研修会参加者は大部分が高齢者です。研修会の最終部分で65歳以上は消防団に採用されないとの説明にだれもがガッカリしました。
平成23年10月1日現在の札幌市の人口は1,904,625人で、このうち65歳以上の高齢者は395,753人、高齢化率は20.7%です。高齢者を年齢別にみると65~74歳までの前期高齢者が206,838人、75歳以上の後期高齢者は187、925人です。一方、15~64歳までの1,283,528人は学業や仕事を持たれ、平日は居住地区での防災活動や災害救助活動に従事するのは不可能です。
防災リーダー中級研修会へ参加する高齢者は、人々の役に立とうとする体力と気力を充実させた方々ばかりです。高齢化社会だからこそ、未来を担う子どもたちや要援護者のために高齢者の力を振り向けるべきじゃないでしょうか。
謝辞:文中に掲載した写真は、プロジェクターで投影されたものを撮影して転載しました。ありがとうございます。