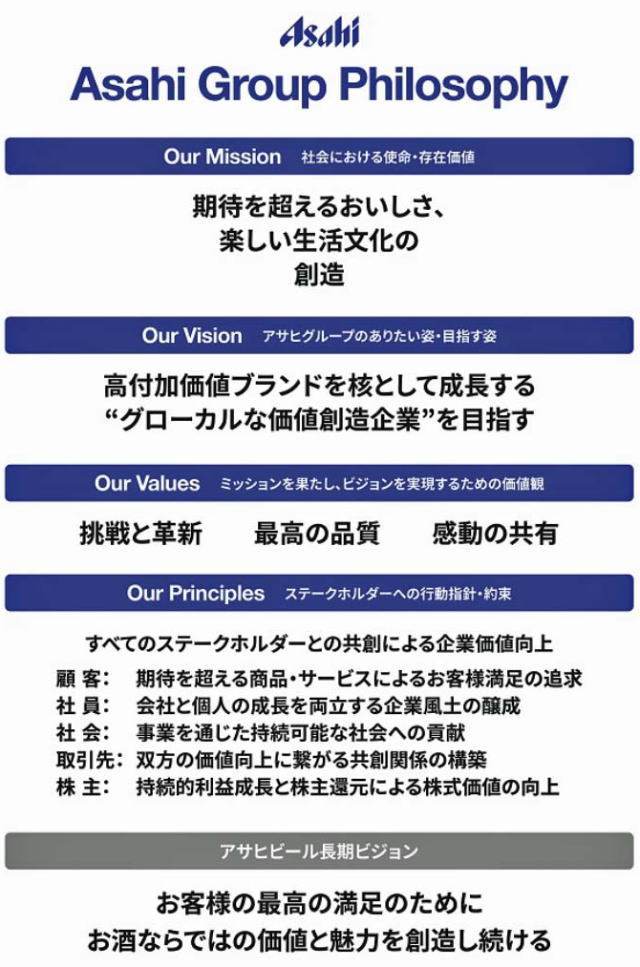3 羅針盤を見よ
3-1 消費者の味覚は
経営理論に制定された「消費者ニーズに沿った商品づくりに徹する」といテーゼにそって、昭和58年頃から新ビール開発へ向けての試験醸造が始まっていた。59年秋頃から5千人の消費者を対象とした大掛かりな嗜好・味覚調査が行われた。
昭和60年に入って、CI委員会の中でもビールの味を見直すべきとの意見が出てきた。ビールの味を見直すためのプロジェクトチームが設置され、食品部長・生産本部長・マーケテイング部長・広報部長などがメンバーに選ばれた。
村井社長になってから朝日ビールのシェアは昭和57年に9.93%と創業以来初めて二桁を割り込み、翌58年に10%代に回復したが、59年には9.93%、60年9.62%とじり貧状態が続いていた。
一連のCI導入活動を眺めながら何か物足りなさを感じていた大阪支店次長の松井康雄が昭和60年8月にマーケテイング副部長に就任すると、このころから味の問題がにわかに加速された。
松井は営業政策の観点からCI計画に大きな渦を巻き起こした。「CIで会社を変身させようとするなら、この際、味も変えなきゃいかんのじゃないか」と言い出し、味の論議に一層の拍車をかけたことだった。
松井は研究所で新しいビール開発へ向けて試験醸造が行われていることも、マーケティング部の行った5千人の味覚調査のことも知っていた。そのうえで、CI委員会に波紋を投げかけたのだった。松井のマーケティング理論は明快だった。
「朝日ビールのシェアが35年以上にわたって落ちてきたのは、一言とでいえばウチのビールに人気がないからだ。役員は『分割の後遺症で東日本に販売網を持てなかったからだ』とか、『サントリーに販売網を解したからだ』とか言うが、それは付帯的な理由だ。
本質的に人気がないから売れない。人気となにか。それは消費者の味覚に合っているかどうかだ。消費者は自分の味覚に合ってなければ、技術的にどんなに粋を凝らしたものでもマズイという。残念ながら朝日は消費者の味覚に合ったビールを作ってこなかった。」
松井の発言は単純明快だったが、自分たちは技術的にも品質的にも第一級のビールを作っているとの自負を持つ生産・開発部門の人たちにはカチンとくる発言である。ケンカ腰のマーケティング論争がCI委員会内で何度も繰り返された。
トップへ戻る
3-2 消費者は何を求める
マーケティング部の行った、5千人の嗜好・味覚調査の目的は驚くような理由だった。「お客さんというのは、ビールの味が分からないものだと思い込んでいたが、実際はそうじゃないのではないか。
たとえ銘柄は飲み分けられなくても、うまいとかまずいとは分かるはずだ。現在の消費者がどんなビールを求めているのか、消費者にとってうまいビールとはどういうものかを調査してみよう」。この調査が新しいアサヒビールを生み出すきっかけとなった。
他社のビールを混ぜて、ラベルを付けたり剥がしたりして実際に飲んでもらう対面調査で、若い世代を中心に大半の消費者が苦みだけでなく、味わいのコクとのど越しのキレを求めている事実だった。
この調査に携わった朝日の社員は意外な発見をした。キリンに代表される苦みの強い重い味のビールがうまさの規準だと思っていたが、必ずしもそうではなかった。「コクとキレを併せ持ったビールをつくれば絶対に売れる」と確信するに至った。
マーケティング部の提案は、研究・開発部はビール開発のコンセプトを根底から覆すものだった。部外の者が味に口を出すことはタブーとされていたが、研究・開発部はマーケティング部の提案をほぼ全面的に受け入れ新しいビールの開発をスタートさせた。
研究・開発部は理想のビールを造らなければ会社はダメになるとの危機感を持ち、営業部門はこの提案はお客様の声だと言う大義名分に支えられていた。しかし、コクとキレというのはビールをつくるうえで矛盾する概念だった。
ビールは90%が水で4.5%がアルコール、0.5%が炭酸ガスで残り5%がエキス分である。エキス分が味を決める秘訣は原料の質と酵母の性質と働きに左右されるので、マーケティング部の注文にあった酵母を見つけ出さなければならない。
朝日ビールの研究所には「酵母バンク」があり、数百種類の酵母が保管されている。その中から選び出されたのが508号酵母である。酵母はおいしいビールができるか否かを決める極めて重要な役割を担っている。
コップ1杯のビールをつくるの約百億個の酵母が働くので、性質のちょっとした違いがビールの出来栄えを大きく左右してしまう。何度も試作品がつくられて営業部門の人たちが試飲し、様々な注文を付けながら改良という作業が続けられた。
トップへ戻る
3-3 沈没の恐怖
酵母はビールの製造過程で発酵の主役となり、仕込み室でつくられた麦汁の糖分をアルコールと炭酸ガスに代え、同時にビールの味わいと風味の成分を生み出す。酵母の大きさは直径わずか5~10ミクロンという極めて性質がデリケートな微生物だ。
それぞれの設計品質に合わせて麦芽とホップなどの原料が選ばれ、独特の方法で仕込最後はの登場する主役が公募で、原料の持ち味を生かしてビールに「狙い通りの香りとコクを付け、キレを醸し出すのが酵母である。
コクとキレのあるビールの開発は営業塗門と割球開発部門が一体となって勧められたがそれを知っているのは村井社長と一握りの役員、部長クラスだけだった。あくまでも極秘のうちに作業は進められ、正式決定するまでは社内外に伏せておく必要があった。
商品の中身を変えると言うことは大変なことだから社外秘というのは当然であり、敵を欺くためにはまず味方を欺かなければならない。妙な形で社内に漏れると社員や取引先の動揺を引き起こす。極秘で作業を進めていくことに一番気を使わなければならない。
その頃のマーケティング部では「いくら会社を変えようと言っても、単なるお化粧直しで会社は変わらない。具体的な変化事実を作り出さなければ。」「マークを変えるのもいい。しかし、それだけでは朝日の変身を消費者に伝えることにはならない。」
「朝日の場合、社会ともっと強力にコミュニケートできる媒体は商品だ。主力商品であるビールの味とラベルを変え、朝日の主張と心を消費者に知ってもらうべきではないか。」「いまこそ味とラベルを一新してマーケットの真ん中で勝負すべきだ。」
マーケティング部の意見にて、CI本部も「新しいビールを新しいラベルで」発売する方向へ傾いていった。しかし、CI本部がそう決めても、会社としての最終決定は常務以上で構成される最高意思決定機関である経営会議の決済を待たなければならない。
昭和60年9月21日土曜日、東京の朝日ビール本社12階会議室で常務以上の経営会議が開かれた。スケジュール的にギリギリのところまで来ている。前週の金曜日の経営会議で「味を変えること」について合意されたが、ラベルの変更は暗礁に乗り上げていた。
関西には古くからの朝日ファンがいる。彼らは今のままの朝日ビールの味とラベルでいいと言っている。もし、ここで味もラベルも変えてしまったら、こうした古くからの朝日ファンを失ってしまうのではないか。地元の支持層が消えることが恐怖だった。
トップへ戻る
3-4 船頭の決断
シェア10%の会社にとって30%近い関西地区は大切な市場である。逆に考えれば、強い関西地区でさえ30%そこそこのシェアしか持っていないということになる。味もラベルも変えないと言う現状維持でいいはずはなかった。
中條営業本部長が大声を上げた。「うちのマークは百年続いた歴史と伝統のあるマークだ。これを見れば誰だって朝日ビールだと言うことがすぐ分かる。そのマークを変えることは失敗したら立ち直れない。だから、みんなが慎重になることはわかる。
しかし、もう堂々巡りの議論をしていても仕方がないじゃないか」。村井社長はその発現を待っていたかのように「では、本部長はこのCIをやれというのか」と畳み込んだ。「ええ、現在のマークでは革新は不可能です。ラベルは変えるべきです。
新しいラベルについて消費者調査の結果も評判はいい。これで何とかいけるはずです」村井社長は次の言葉で会議を締めくくった。「たしかに味やラベルを変えることはみんな怖いだろう。しかし、この決断にはCIの成否、ひいては社運がかかっている。
本社なり経営ボードがリーダーシップを発揮しなければ一歩も進まない。そのためにはやってみる価値を認めたならば、やり抜くんだという強い決意が必要である。それが経営というものだ。我々は経営者なのだから、いまこそ思い切ってやるべきである。
ここまで追い込まれた以上は、背水の陣で全力を傾けてやると言う考えが必要でないのか。もし、失敗したらどうするのかという心配もあるだろう。その時は、会社を辞めてから謝ればいいじゃないか」。こうして経営会議において正式に決定された。
翌々日の支店長会議で村井社長は次のようなゲキを飛ばした。「古い組織には風化現象というのがある。それを打破するには組織の活性化が必要だ。そのためには新たな価値観が必要である。そう考えて我々は経営理念をつくった。
このままでは会社はあかんという危機感がみんなにあるだろう。しかし、まだ甘い。まだまだ君たちは眠っている。理論ばかりが先行して、手足が動いていない。ここまで追い込まれたら、かえって反攻のチャンスだ、と考えるべきである。
支店長はガタガタ理屈ばかり言わずに陣頭指揮をせよ。具体的に何をやっているのか、もっと機敏な対応が必要だ。組織の風通しがよくなければ、機敏な対応ができない。本社と支店が力を合わせれば必ずニューアサヒは復活する。私はそう確信している」。
トップへ戻る
3-5 新たなる出発
村井社長は来年の3月で68歳を迎える。社内の盛り上がりを感じた村井社長は就任してからの4年間を振り返り、味もラベルも変えるのだからこの際、若手の社長を迎えることを決意し、住友銀行で後輩の樋口廣太郎の姿を思い浮かべた。
気心は知れているし仕事はできる。俺が会長で樋口君が社長になれば会社はさらに発展するだろう。住友銀行の磯田頭取に樋口のもらい受けを頼むと、話はトントン拍子に進んで年内に村井会長と樋口社長の人事が内定した。
朝日ビールの仕事始めは1月6日だったが、樋口はその日から顧問として出社した。本来は3月の株主総会終了後に出社することになるが、それまでは待てないので指揮を執らせてくれと村井に顧問の肩書を付けてもらった。
樋口は経営会議にも出席し、社長としての発言もした。社内の事は樋口、対外的な仕事は村井と役割分担がはっきりし、二人の間に相当に強い信頼関係があるので二頭政治の心配は初めからなかった。
樋口は朝日ビールにくるまで「ビールの味を変える」ということをしらなかった。それを知らされた日から2日間、眠れぬ夜を過ごした。というのは、かってコカ・コーラがペプシ・コーラの攻勢に対抗して「味の変革宣言」を行い、味を変えたことがある。
ところがそれが失敗し味を元へ戻した。コカ・コーラは失地回復に塗炭の苦しみを味わい、その窮状を樋口は目の当たりにしていた。樋口は、食品会社が味を変えることがどんなに危険なことか知っていたのである。
すでに朝日ビールの方向は決まっていた。樋口は吹田工場の地下三階にある歴代社長ですら入ったことがない酵母の貯蔵室を訪れ、一日も早くうまいビールをつくってもらいたいと技術者を激励した。その数日後、樋口は感動的な光景を目にした。
新製品が2月中旬からの発売が決まり、技術部と営業部の部長以上がこれまでの慰労を兼ねてパーティを開き、樋口も招待された。会場へ入ると、今回の新ビール開発を通して技術屋と営業が心を割って話し合えたことがうれしいと男同士が抱き合って泣いていた。
朝日ビールのCI導入がマスコミを通して世間に発表される前日の1月21日、対外発表に先立ち社内セレモニーが開かれた。各職場で新しい社章(バッジ)と名刺が配られたのち村井社長のメッセージが伝えられた。
トップへ戻る
3-6 帆を上げろ
「いままでは社内議論だったが、明日からは白日の下にさらされる。いまさらどうこうと細かいことは言わないが、これからは世間の我々アサヒマンを見る目も変わってくる。それを肝に銘じてもらいたい。」
翌日、マスコミにCI導入を発表すると同時に、全国紙、ブロック紙、地方紙などに全15段を使った企業の宣伝広告が掲載された。これは企業変身へ向けての高らかな社外宣伝であり、社内を一層駆り立てて行こうとの狙いもあった。
翌1月23日と24日は、全営業マンを対象にした「ビアコンべション」が行われた。通称「社内ハッスルパーティ」と呼ばれる営業マンたちの決起集会だったが、朝日ビールにとってはいままでにない大掛かりなものだった。
この日から3日後に、発売に先立ち全事業所一斉に新ビールの試飲会が実施された。全社員を対象とした試飲会は朝日ビールにとって異例中の異例だった。社員の立場ではなく、消費者の立場で飲む。自社のビールがうまいと気付けば自信につながる。
社員試飲会を実施するにあたって、裏方さんたちがもっとも気を使ったのは秘密保持である。まだ新ビールは対外的に発表していないので、運搬と管理には十分注意して運ぶ時には目隠しをし、飲んだ後の空瓶や空き缶はきちんと回収して捨てずに保管した。
社外へ持ち出されると他社に知られてしまう。新ビールが対外的に公表されるのは2月3日である。この日から3日間、仙台を皮切りに全国五つの都市で特約店と問屋の販売課長以上の「ライブ・コミニュケーション・パーティ」と銘打った特約店会が開催された。
村井や樋口は「いままでは我々の努力不足で、朝日を応援して下さるみなさんのご期待になかなか添えなかった。しかし、これからは違う。この商品の発売をきっかけに朝日は生まれ変わります。どうか今後ともアサヒビールをよろしく。」と挨拶して回った。
準備するスタッフはほとんど3日間徹夜だった。発売前のビールを極秘でホテルへ持ち込み、パーティが始まるまでホテルの冷蔵庫で冷やしていおく。ぬるければ話にならず、冷えすぎてもいけない。スタッフは細かい温度管理もチェックしていた。
発売の日、ほとんどの販売店から前の朝日ビールは消えていた。「何もそこまでやらなくても」という酒販店からの意見もあったが、新しいビールの発売に合わせてアサヒビールは数億円かけて朝日ビールを市場から回収していた。
トップへ戻る
 れ続ける「波」に「朝日」のマークで、このマークには朝日ビールの創業の精神がこめられていた。
れ続ける「波」に「朝日」のマークで、このマークには朝日ビールの創業の精神がこめられていた。