1 拓殖銀行の民事提訴
北海道拓殖銀行が営業を終了する11月13日の午後1時45分、拓銀代理弁護団の弁護士7名が拓銀を経営破綻へ導いた旧経営陣の責任を問うため札幌地方裁判所へ訴状を提出した。訴状は5案件約200頁に及ぶ膨大な内容だった。
訴えでは、建設不動産業「カブトデコム」(札幌)、拓銀関連の「エコスリース」(札幌」、料亭経営と不動産業「日伯」(大阪)、内装・看板工事業「ミヤシタ」(帯広)、不動産業の「栄木不動産」(東京)の5企業に対する融資にかかわった11人の拓銀旧役員が、ずさんな融資で銀行に損害を与えたとして108億円の賠償金が求められた。
拓銀が破綻した日に訴状が出されたのは、鷲田秀光頭取代行を始めとする最後の首脳たちの固い決意だった。首脳たちは懸案だった経営責任問題を「拓銀」の看板があるうちに決着をつけたいと考えた。週明けから再出発する「けじめ」をつけるためである。
| 問題とされる融資先 | 損害の内容 | 対象となる被告 | 賠償請求額 |
|---|---|---|---|
| カブトデコム | 685億円 +192億円 | 山内元頭取・河谷元頭取他8人 | 総額50億円 |
| エスコリース | 約137億円 | 山内元頭取・河谷元頭取他5人 | 総額30億円 |
| 日伯 | 約39億円 | 鈴木元頭取・山内元頭取他3人 | 総額10億円 |
| ミヤシタ | 約14億円 | 鈴木元頭取・山内元頭取他7人 | 総額 8億円 |
| 栄木不動産 | 約61億円 | 山内元頭取他5人 | 総額10億円 |
| 合計 | 約1,128億円 | 総額108億円 |
山内、河谷両被告は懲役2年6カ月の実刑判決が言い渡された。最高裁の判決を受けて整理回収機構側は年金など生活に必要な分を除き、「すべて資産を投げ出した」と判断されるまで賠償金の支払いを求めた。
訴えの対象となった旧役員は、鈴木茂、佐藤安彦、山内宏、河谷禎昌らの元頭取をはじめ、海道弘司、秋田甫、武馬鋭稱、藤野公毅、中村弘二、大野忠二、広瀬恭平、八木一郎、志田光弥の各氏は、応分の賠償金を負担することになった。(一部は和解済み)
しかし、カブトデコムの元社長佐藤茂氏は、逃避させたカブト資産を米国子会社を使って転売や売却を重ね、海外で悠々自適の生活をしているという噂がある。佐藤茂氏や日産のカルロス・ゴーン氏のように、海外へ逃亡すると警察は手も足も出ないのだろうか。
1-1 バブルを生んだ金融機関
戦後、疲弊した国土と経済の復興を支えるため国は強力な行政主導の金融政策を行い、大蔵省が各銀行の過度な競争を抑えて金融機関全体の存続と利益を実質的に保証し、最弱の銀行に他行の足並みをそろえさせるという護送船団方式を取っていた。
94年に大蔵省が拓銀に対して行った金融検査の報告書の特記欄に「拓銀は不動産業者に約60億円を融資したが、暴力団関係者に実質的に経営を支配されたため、大半が回収できなくなった」ことが記録されている。
さらに「この不良債権の処理が遅れた背景には拓殖銀行員と不動産業者との間に個人的な関係があり、拓銀がこの事実を知られるのを避けようとした点があった」と記録されている。過去の銀行首脳の女性問題のスキャンダルを握られていたらしい。
98年9月にまとめられた拓銀与信調査委員会の調査報告書にも「顧客が拓銀役員等の不祥事を掌握していることを背景に融資が行われている」と指摘している。拓銀関係者にも「担保不足でも融資が行われる異常な取引」と認識されていた。
拓銀は産業構造の転換に対応しきれず破綻に追い込まれた岩倉組や函館ドックに対する巨額の不良債権処理を迫られ、都市銀行の中で業務と収益力の両面で最下位にとどまり、地方銀行のトップがひたひたと迫ってくる状態だった。
日本の護送船団方式は海外から痛烈な批判を浴び、金融機関が自由に金利を決め、業務の垣根をなくし、欧米と同じルールでビジネスを行うと言う金融自由化の流れが外圧によりもたらされた。80年代の金融自由化の荒波は銀行経営にとって冬の時代となった。
さらに、銀行にとって痛手だったのはこのころ大企業の銀行離れが進んだことだった。証券市場が活性化し、大企業は銀行に頼らなくても国内外の証券市場を通じてコストの安い資金を調達できるようになっていた。
銀行は、預金獲得に血道をあげても低金利でもうからない。融資したくても貸し先がない。規制金利時代に銀行は預金という資金量さえ伸ばせば、自動的に儲かると言う仕組みだった。この経営手法は自由金利の下では手詰まりとなっていった。
住友銀行が先頭を切って高収益を上げるためなら、多少の粗っぽさを容認したプロジェクト融資や不動産融資で派手に稼ぐと言う方式が急速に各行の間に広まっていった。徹底した効率化と収益重視の新しい経営手法は当時の銀行業界では革命的だった。
住友旋風に対抗しようと各行も相次いで追随し、銀行同士が激しく競い合う収益競争の時代が幕を開けた。これがもとになり、85年前後から銀行の資金が土地や株に流れ込みカネがカネを生むバブルの再生産が始まった。
激しい嵐のような時代に都市銀行の中では業務・収益力ともに最下位だった拓銀は焦っていた。収益競争の激化で上位行との差は広がり、一方で地方銀行上位行に激しく追いあがられ一部有力地銀にも逆転を許してしまった。
景気の波はいつも北海道には遅れて届く。一般消費者を巻き込んだ株式ブームや不動産ブームが道内で始まったのは、首都圏、関西圏よりワンテンポ遅れていた。ようやく拓銀が他行並みに不動産融資を加速させたのは88年ごろとされ、完全な出遅れだった。
バブル期路線の中核となる鈴木茂・佐藤康彦・海道広司のSSKラインは、過去の銀行首脳の女性問題スキャンダルの後始末を契機として連帯したが、不動産管理業者やエスコへの拓銀融資は焦げ付き、拓銀は合わせて数百億円の実損を被った。
拓銀は、米国の経営コンサルタント会社マッキンゼーに「21世紀ビジョン」の策定作業を依頼した。ビジョンの大枠は、道内でのリーディングバンク戦略、本州でのニューリテール小口金融戦略、そして国際部門でのアジア終点戦略が三本柱だった。
このビジョンには目玉がないとの意見が出て、急遽伸び盛りの新興企業を卵のうちに発掘して大きく育てようと「企業成長支援、不動産開発機能路線」の柱が付け加えられた。しかし、付けたしだったはずのこれらの柱はいつのまにか主役に祭り上げられていった。
鈴木頭取時代に一気に火が付いた不動産融資への傾倒は山内体制でも受け継がれ、90年9月8日の記者会見で拓銀の山内宏頭取は、自信に満ちた表情で策定に十ヶ月の期間と約三億円をかけた「21世紀ビジョン」を説明し、総合開発部が設けられた。
90年10月1日の東京兜町では、多くの証券マンが株価を示すボードの前でため息をついていた。この日、東証の平均株価が3年7ヶ月ぶりに2万円の大台を割った。そんな中、大通公園に面した拓銀本店四階の一室は異様な熱気を放っていた。
伸び盛りの五十数社を所管する新戦略部門として拓銀内の大きな期待を集めていた総合開発部の部員の表情は自信に満ち、カブトデコムやソフィアなどバブル企業への巨額融資にのめりこんでいった。
しかし、このころになるとバブル経済は崩壊期に差し掛かり、不動産プロジェクトに大量に投入されていた貸付金が不良債権化し、地価や株価の下落と共に内包する損失額が膨れ上がっていくこととなった。
その後も相場は回復せず地価は下落の一途をたどったが、拓銀は手を染めたプロジェクトから撤退すると言う的確な判断をすることができず、次々に追加融資をしていったことが損失の拡大に直結することとなった。
バブル案件の失敗が明確になり、いかにして損失を処理するかという不良債権処理計画の立案と推敲が最大の経営課題となり、拓銀のバブル型不良債権発生の中心となっていた総合開発部は廃止された。
95年7月の日銀考察で将来最大8千億円程度の処理が必要と認識されるようになり、米国Moodys社が公表した財務格付けでは最低のEランク(最終的には何らかの外部の支援を要する格付け)に格付けされた。
平成9年4月1日に拓銀は海外業務から全面撤退して北海道銀行との合併を模索したが不良債権処理方針とシステム等についての合意には至らず、取締役会で自力での経営再建を断念して合併の白紙撤回と営業譲渡を議決して創業百年を前にその幕を閉じた。
都市銀行の経営破綻は国内初のケースである。その時点で拓銀は預金量5兆9千億円、公表不良債権9千3百50億円という日本金融市場最大の破綻となった。河谷頭取は自力再建を断念して、道内の預金や貸し出しなどの営業を北洋銀行に譲渡すると発表した。
一方、突然の営業譲渡で北洋銀行の武井頭取は「先週の土曜日夕方から拓銀と大蔵省、日銀の強い要望があり、数時間で譲渡受け入れを決断した。このまま放置すれば北海道経済が大混乱してしまうという広い見地に立って決断した」と経緯を説明した。
1-2 日本の金融史上悪夢の月
11月15日(土曜日)、東京都千代田区のパレスホテルでの取締役会決定が札幌市の本店に伝わると、11月17日(月曜日)への対策が始まった。取り付け騒ぎに備えるため、日本銀行は拓銀の預金の2%に当たる現金800億円を用意するよう指示した。
拓銀が準備できたのは360億円で、不足分は日銀特融を利用し、事前に道内134の拓銀本支店へと運び込んでおく必要があった。11月16日(日曜日)夕方から現金輸送が始まり、各支店への作業が終わったのは21時である。
同時に本店勤務員の各自宅に連絡が入り、翌朝7時までに支店の応援に向かうよう伝えられた。深夜の拓銀本店では、取引先への配布文書・店頭ポスター・記者会見の想定問答集などの準備が整いつつあった。
この日だけで解約された預金は600億円、11月19日までの3日間で4,900億円に上り、預金解約の際に使われる伝票や払戻請求書が底をついて、近隣支店からの融通も利かず、止むなく複写機で複写した帳票を使って対応せざるをえない状況だった。
97年11月は日本の金融史上に残る「悪夢の月」で、3日に三洋証券、17日に拓銀が破綻。拓銀の主幹事を務めていた山一證券も11月24日に自主廃業を決定。翌98年には、拓銀が設立に協力し大株主でもあった日本長期信用銀行も連鎖倒産している。
2 バブルの寵児
2-1 カブトデコム
兜建設は1988年にカブトデコムという奇妙な社名に変更した。創業時の社名であるカブト(兜)に、Development(開発)、Construction(建設)、Management(経営)の頭文字 DECOM を組み合わせて新社名としたのである。
本来は建設業だったが、土木工事から不動産の売買・賃貸へと年を追って業態が変化していった。グループを率いていたのは44歳の若き佐藤茂社長で、カブトデコムの設立当初のメイン銀行は信用組合であった。
北海道の建設業者がもっぱら公共事業の受注を収益の柱とする中、カブトは「民間物件の開発提案企業」を掲げて急成長を遂げていた。89年に154億円だった売上高は90年に418億円、91年に1,009億円と千億の大台に乗せていた。
この当時、カブトデコム及び子会社と関連会社等の事業システムの問題性は周知され、子会社と関連会社等との業績は必ずしも判然とせず、子会社と関連会社との間で不明瞭な資金操作が行われている可能性があり、不透明な部分も指摘されていた。
しかし、75年5月にカブトデコムは拓銀に株式と転換社債等を引き受けてもらいたいと申し入れた。カブトデコムの佐藤茂と当時の拓銀常務取締役であった佐藤安彦が面談した結果、佐藤茂の構想に引き込まれて申し入れを受け入れ拓銀はメイン銀行となった。
カブトデコムの事業システムは極めて特異なもので、急成長の裏側にはあるからくりが隠されていた。山三西部地産、丸三昭和通商といった地上げ部隊の関係会社に土地を取得させ、それらの会社からカブトデコムが建物の建築を受注した。
建物の完成後、その土地と建物を一括してカブトデコムが買い上げ、それを再び子会社や関連会社などに転売したり賃貸する。これにより、カブトデコムは建築受注代金と土地・建物売却代金の両方を売上に二重計上していた。
売上二重計上は、どこかで資金繰りが悪化すると瞬く間に全体に波及する。自らの事業資金の資金繰りの他にグループ会社の地上げ資金、物件購入資金にも債務保証という形で偶発債務を背負わざるを得ず、佐藤茂は事実上グループ全体の資金繰りを担っていた。
カブトデコム本体とグループ企業は互いに連鎖していて、カネが内部で回転し続けてこそ信用力は維持され、成り立つと言うものだった。カブトデコムが描いたその円環の構図はバブル崩壊で急激に回転が鈍くなっていた。
事業自体が本来的に自転車操業であり、これが円滑に回転し事業として成立するためには、事業物件についての地上げ、上物建設、売却処分といった一連のプロセスの回転が速いことと、含み損しないよう不動産価格が右肩上がりで上昇し続けることが必要だった。
しかも金融機関等からの資金調達が潤沢かつ円満に行えることなど、三つの必須条件を具備している必要があった。当然のことであるが、これらの条件の具備は事業規模が大きくなればなるほど容易なことではなく、カブトデコムの業績は悪化の一途をたどった。
海道弘司が佐藤安彦にカブトデコムの実情を打ち明けたころには、拓銀からカブトデコムへの融資残高は表面上は500億円程度とされていた。カブトデコムの経営悪化の深刻な実態を、副頭取の佐藤を始め拓銀幹部はほとんど認識していなかった。
92年3月末にカブトデコムに対して500億円の追加融資枠を設けることが決まり、カブトデコムの救済融資額は以後5ヶ月余りで540億円にも上った。新興企業育成路線の象徴だった海道弘司は常務を退任し、引責人事で関連会社の社長に就任した。
拓銀とカブトデコムの互いのグループ企業で行われた融資を含めた相対の融資額は膨大なものとなっていた。拓銀の緊急調査で92年9月時点で、カブトグループ全体の借入金は5,198億円、内拓銀グループからの融資は2,803億円に達していた。
拓銀とカブトデコムの互いのグループ企業同士で行われた融資額は数千億円となり、拓銀が割当先企業に株式取得資金として200億円を融資したが、この融資先の中には幽霊会社や経営破綻した会社も含まれていた。
さらにカブトデコムが関連会社などに対して行った債務保証の額は、表面上は302億円と報告されていたが、実際はその3倍以上で1,000億円を越えていた。10月26日に拓銀本店で山内頭取はじめ5人が集まり経営会議が開かれた。
この経営会議で、表面上はカブトデコム支援の姿勢を装いつつ、裏側では降りかかる悪影響を最小限にとどめる道を探りながら、数か月後にはカブトデコムを倒産に導くこととなった。
拓銀本支店から拓銀のダミー会社へ一社当り10億円、100億円単位の融資が行われて経営悪化の著しいカブトデコムとその周辺会社へ、拓銀が資金を捻出するための事実上の迂回融資の受け皿として利用された。
ダミー会社からカブトデコム本体を含むグループ会社へ再融資された資金は、これらの会社からたくぎんファイナンスやたくぎん抵当証券などへの借入金返済に充てられた。不良債権をダミー会社に移し替えて見かけ上消し去る不良債権飛ばしである。
カブトデコムは業務拡大の一環として88年に総事業費665億円、通年営業の会員制リゾート施設を運営する構想を立て「エイペックスリゾート洞爺」と称した。甲観光を事業主体としてカブトデコムが甲観光から工事を受注して鹿島建設に丸投げ発注した。
88年12月に甲観光はコンドミニアム新築工事、スキーセンタービル新築工事、ロープウエイ駅舎新築工事をカブトデコムに発注し、さらに89年11月にホテル建設追加工事を発注した。
拓銀は単純な資金提供に留まらず、計画段階から行員を派遣して会員権の販売に関与したり、たくぎん保証会社が約250億円の債務保証をするなど、全面的にエイペックスリゾート洞爺事業を支援した。
しかし、このころには拓銀とカブトデコムの断絶は明らかになっていた。拓銀はカブトグループ企業で収益力のある「甲観光」と「兜リッチフィールド」を自らの参加に収めてカブトデコムグループとは異なる支援を表明していた。
エイペックスリゾート洞爺の完成披露のあと、拓銀は兜リッチフィールドの株式総会で動議によりカブトデコム出身役員を解任して経営権を奪い、カブトデコム所有の筆頭株を担保権行使により名義を拓銀に書き換えさせた。
拓銀はこれにより手中のおさめたエイペックスリゾート洞爺と兜リッチフィールドに、カブトデコムの元社長佐藤茂を手形偽造で刑事告発させた。拓銀の思惑は刑事告発取り下げと交換条件に佐藤茂をカブトデコムの社長退陣させることだった。
カブトデコムは拓銀側の要求をほぼ全面的に飲み、佐藤茂の社長退陣と個人資産没収などを容認したが、札幌地検は告訴取り下げを認めず、告訴を取り下げるなら拓銀の特別背任を立件するとした。
札幌地検は、拓銀からカブトデコム周辺に対し、さらにカブトデコムから政治家に対して流れていたカネが存在するのではと考えていた。刑事告訴は当事者の内部に踏み込む足掛かりとして好都合だった。佐藤茂は一審で無罪判決を受け札幌高裁で控訴審が継続中。
2-2 エスコリース
エスコリースは66年3月5日に設立され、その主な営業を当初は機械及び車両などのリースとしていた。75年に土地投機に失敗したことなどから経営が破綻し、拓銀と日本リース株式会社の支援の下で再建することになった。
75年1月に拓銀はエスコリースに資本参加をするとともに人材を送り込むこととし、エスコリースの代表取締役社長として拓銀OBであるHを、エスコリースの取締役として拓銀の行員であったIを派遣し、エスコリースとの間で銀行取引約定書を交わした。
平成3年4月30日に拓銀は、エスコリースに対しエスコリースの外国銀行に対する約定弁済金及び国内銀行に対する利息金の支払のための資金(いわゆる肩代わり資金)として37億円を融資した。
さらに拓銀は、エスコリースの運転資金として91年6月2 8日に22億8700万円を融資し、同年7月24 日に2億8700万円の返済を受けた。同年7月31日に7億円を融資した。
エスコからECCへの融資は、わずか数年の間に爆発的に膨張した。エスコは拓銀からの570億円をはじめ、30余りの金融機関から2千数百億円を借り入れ、その大半の2千億円以上をECCに集中的に注ぎ込んでいた。
この異常なまでの巨額な金の流れの裏側で、実は数百億円が使途不明となっているが判明したのは少し後になってからだ。ECCからは大蔵省の元主計局次長に数千万の資金提供や、政官界の有力者にばらまかれていった。
エスコリースから約2千億円借り入れていたECCは、91年に経営が行き詰まり利払いもできない状態に陥った。93年春、拓銀はエスコに融資していたその他の金融機関を説得して、元利払いを一時猶予する金融支援策を打ち出した。
猶予期間中にエスコがECCからの債権回収を図るというのが狙いで、拓銀は92年3月31日、エスコリースの国内銀行に対する弁済金の支払のための資金(いわゆる肩代わり資金)として80億6500万円を融資した。
債権回収は一向に進まず、業を煮やした拓銀はECCからの強制的な回収に動いた。ECCはその動きに対抗するように、大阪地裁に和議申請して自ら倒産する道を選んだ。債券の大幅カットが確実な和議はエスコや拓銀などにとって圧倒的に不利になった。
2-3 日伯株式会社
日伯は昭和25年4月11日に設立され(なお、設立時から昭和63年2月5日までの商号は「日伯貿易株式会社」であった。)その主な営業目的を飲食店や旅館の経営とする株式会社である。
かつてKが日伯の経営する料亭で板前として勤務していた経緯から、Kの 紹介により拓銀は昭和56年から日伯の代表者L個人と与信取引を始め、 昭和58年11月から日伯と与信取引を始めた。
日伯はECCから、昭和62年7月3日ころに35億円を借り入れてゴルフ場建設計画に着手した。拓銀は昭和62年に日伯に対し、日伯のECCに対する上記借入金などの支払のための資金として、39億2000万円を融資したが回収不能となった。
2-4 ミヤシタ
株式会社ミヤシタは、帯広市に本社を置き、内装、看板工事を主な業務して71年3月に設立。78年からは長崎屋の北海道における指定事業者になり、北海道の長崎屋と関連会社の内装工事をほとんど受注する関係となった。
97年11月にミヤシタから長崎屋株の仕手戦の資金として拓銀に20億円の借り入れ申し込みを行なったが、仕手株の融資は社会的に問題があるとの理由で直接の融資は行なわれなかった。
その際に既存借入の実績を理由に7億円(翌年には9億円に拡大される)の運転資金限度枠を設ける事により、事実上、拓銀は仕手戦の資金とされることを容認した。
平成に入ってから、子会社の有限会社コウシン商事が88年以降に行なっていた小豆相場取引を本格化するため、89年1月から2月にかけて拓銀に小豆相場運転資金の融資を申し込んだ。
拓銀から有限会社コウシン商事は合計27億5千万円の融資を受けたが、翌年の90年3月までに小豆相場の損失16億5千万円が発生する事となる。
10月には小豆相場での損失を挽回するために乾繭(かんけん)現物取引を画策し、その必要資金として15億円(その後24億まで拡大される)の融資を依頼したが、拓銀は直接の融資は不可能とした。
拓銀の子会社であるたくぎんファイナンスサービスが、拓銀に代わってて融資をする事となったが乾繭現物取引は失敗に終わり92年に事実上倒産した。
2-5 栄木不動産
拓銀が実質的に既に無担保で約48億円を融資してしまった栄木不動産に担保の提供を要求したところ、20億円の追加融資をすれば不動産を担保提供すると言われ、検討期間わずか数日の26日には総額約20億円の融資を決定し実行している。
拓銀の会議の席上で、「20億円の追加融資に応じなければ拓銀が担保を取得できず、48億4千万円の保全ができなくなる、栄木不動産は3月にも不渡りを出す可能性がある」などの意見がだされた。
栄木不動産はこの約48億円について仕手戦に費消していたことも分かっていた。このように健全な貸付先とは到底認められない債務者に対する融資として新たな貸出しリスクを生じさせるものであり、原則として受入れてはならない提案であった。
裁判所は、20億円の追加融資の実行判断は取締役らの忠実義務違反と善管注意義務違反があり、回収不能により生じた損害につき責めがあるとしたが、栄木不動産は拓銀に対し10億円及びこれに対して各支払済みまで年5分の割合による金員を支払えと命じた。
2-6 ソフィア
ソフィアの創業者は理容師の中村揚一である。貧しい家庭で育った中村は旺盛な向上心を持ち、1872年に札幌駅近くのホテルに「サウナのある理容室」を開業。奇抜な店舗展開で道内外に30店を構える「ソフィア中村チェーン」を築いた。
80年代の半ばに中村が積極経営に乗り出した時期、ソフィアのメインバンクは北洋相互銀行だったが急拡大を続けるソフィアに北洋側が懸念を示していた。拓銀は道内の成長企業発掘を進めてソフィアの評判を聞いて近づいてきた。
拓銀とソフィア両者の思惑は一致して、ソフィアのプロジェクトに拓銀は潤沢な融資を行った。札幌市北区における大規模再開発事業を打ち出し、88年にヨーロッパのクアハウスをモデルとした健康リゾートホテル 「札幌テルメ」を開業した。
91年には隣接地に地上11階建ての「テルメインターナショナルホテル札幌」の建設に着手して93年に開業した。総事業費は当初計画で60億円だったが実際は260億円にまで膨らみ、国内初の都市型健康リゾートが完成した。
地上11階建て、収容人員550名、全フロアを貫く巨大なガラス張りのアトリウムと3000人収容の大ホールを含むテルメインターナショナルホテル札幌の建物は、うすいピンク色を基調といた豪華な外観で、玉ねぎ畑に囲まれて奇異な印象を与えた。
さらにはヤオハンと共同で巨大ショッピングセンター建設を計画するが、市街化調整区域による制約や農地法違反疑惑の影響などから実現せずに94年に凍結。いずれも拓銀グループが資金を捻出し、総事業費1千億円前後、総面積は90ヘクタールに及んだ。
ソフィアグループは拓銀破綻以降に温浴施設経営のワンディ・スパなどに分かれたが破綻し、学校法人中村学園札幌ビューティ・メイク専門学校が唯一と言っても良い事業として継続されていた。
しかし、その専門学校も継続が難しいという判断があって、生徒たちは他の類似の学科を擁する専門学校に振り分けられ、学校法人中村学園は法人格のみを残す事業体になっているという。
拓銀の経営破綻後は施設の売却先を探すが不調に終わり、98にホテル経営の「テルメインターナショナルホテルシステム」、札幌テルメ経営の「タウナステルメ札幌」、資産管理会社の「ナカムラ興産」が破産宣告を受けて施設は閉鎖になった。
当時の拓銀会長と頭取、それに中村氏の3人が特別背任と任務違背を問われた。拓銀の首脳陣は回収の見込みのない融資で銀行に計85億7千万円の損害を与えたとして特別背任罪で起訴され、ソフィアグループの中村揚一被告も約47億円分を共謀したとされた。
破産管財人は複数の企業と任意交渉を試みるが実現せず、整理回収機構の申立てにより不動産競売にかけら、2001年に再入札によって「シャトレーゼホールディングス」が14億1.650万円で落札し、ナカムラ興産などと売買契約を締結して取得した。
シャトレーゼは施設の改修を行い「シャトレーゼガトーキングダムサッポロ」として開業(旧札幌テルメは「スパ&リゾートフェアリー・フォンテーヌ」、旧テルメインターナショナルホテル札幌は「オテル・ド・レーゼン・サッポロ」と改称)した。
シャトレーゼホールディングスは、シャトレーゼ周辺を「お菓子の街」のテーマパークにする構想を持っていたが、市街化調整区域であるために交渉が進展しなかった。
刑期を終えた中村氏は、新たな学科を設置して専門学校を再スタートさせたい意向のようで、一部には元北海タイムスオーナーで京都科学技術専門学校を運営していた山崎種三氏との連携を模索しているとも言われる。
3 拓銀関連企業の末路
たくぎん抵当証券は84年に設立された。バブル景気で、最盛期の93年には融資残高5281億円まで拡大したが、バブルの崩壊で3438億円がの八割が不良債権化した。拓銀が追加融資や債券の一部放棄などで支援したが2052億円の債務超過に陥った。
拓銀の経営破綻が発表された翌日、11月18日にたくぎん抵当証券は札幌地裁に自己破産を申請した。抵当証券は、拓銀行員も顧客に斡旋した商品だったが預金保護法の保護対象とはなっていなかった。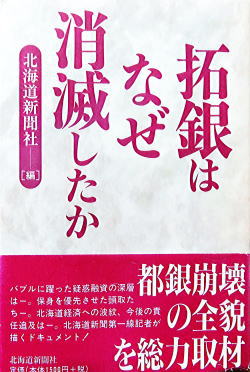
たくぎん抵当証券の負債総額は、北端夕張炭鉱の721億3千万円を抜いて5391億円という北海道史上最高額、全国でも6番目という大型倒産となった。
売掛債権の買い取り業務を目的に78年委設立したたくぎんファイナンスサービスは、80年代半ばには不動産融資に傾倒し、ピーク時の92年には年間売り上げ243億57百万円、営業貸付金が7千7百億円となった。
バブル崩壊で、近畿建設(倒産負債千百珀10億円)、八代コーポレーション(倒産負債千百40億円)、など融資先企業の相次ぐ倒産で不良債権が累積していき、たくぎん抵当証券に注ぐ負債総額2百57億円で札幌地裁に特別清算を申請した。
拓銀から不良債権を押し付けられた、たくぎん保証(負債額508億円)、不動産業のティ・エイ・しー・ティ(負債額975億円)、ベンチャーのたくぎんキャピタル(負債額305億円)など、関連不動産業者が倒産した。
4 行員の再就職
拓銀破たん時の行員は道内で3,357人、道外で1,813人で、ある程度は北洋銀行に移ることは確かだったが、北洋銀行は雇用を守るとの空手形は切れず、2,000人の北洋銀行を上回る規模での再雇用は望めなかった。
中央信託銀行は1,200人を引き受けたが、中央信託銀行は三井信託銀行と合併して行員2,000人を削減した。整理回収銀行は265人を受け入れ、日本アイ・ビー・エムが484人を採用したが、中高年1,200人が退職した。
雇用対策センターには2,454人の求人が寄せられたが、対象者は20~30代に集中していた。働き盛りでしかも住宅ローンや教育に金がかかる40~50代の求人は数えるほどしかなかった。
しかし、拓銀関連企業の職員200人以上と、その関連企業を含めると数百人以上は路頭に迷うことになった。いずれも親銀行である拓銀から不良債権を押し付けられた不遇の子らの再就職は思うように進まなかった。
5 道新の指摘
北海道新聞社は、1999年3月1日に「拓銀はなぜ消滅したか」を世に問うた。この本の第7章で後半で次のように述べている。
定期的な検査で経営の隅々まで把握し、かつ決算承認銀行として経営にも大きく影響を与えていた大蔵省はしかし、拓銀の経営実態の真実を公にすることは破たんまでついに一度もなかった。大蔵省は拓銀の経営悪化を知りながら、一体、具体的にどんな指導をしてきたのだろうか。
拓銀の経営について、大蔵省は銀行法などで定められている権限を十分に生かさずに、適切な監督と改善指導を怠ってきた。三塚博蔵相は97年2月の衆議院予算員会で「大手20行をしっかり支えるのは当然のこと」と述べ、拓銀を含む大手銀行の破たんはありえないと名言しておきながらその言葉をほごにした。
不良債権処理の先送りという無責任行政を棚に上げて、資金繰り破たんの側面をことさら強調して自らの責任を回避した。拓銀が破たんした結果、受け皿となった北洋銀行と中央信託銀行への資金援助などに、3兆4千百13億円の公的資金が預金保険機構から投入された。
金融のグローバル化の伸展とデフレ経済の中で、もはや大蔵省がやって来たような先送りの手法をとる余地はない。日本の金融の再生に向けて金融行政の無責任体制がどう改善されていくのか。民間金融機関の自動改善努力が求められている一方で、責任の所在とルールを明確にした金融行政の確立もまた焦眉の急の問題なのである。
6 誤算だらけの政府
当時の金融市場関係者の間で、「大蔵省が本腰を入れれば拓銀はまだ延命できたかもしれないが、日本の新しい金融秩序をつくらせるためには多少の犠牲はやもうえず、拓銀をスケープゴーストにして市場のなすがままにさせた」という見方があった。
日本の金融システムを守るために都市銀行は1行たりとも潰さないと胸を張っていた政府・大蔵省が、世界的な金融ビッグバンを乗り切るためには大手の都市銀行といえども自助努力のないものは淘汰されると突き放した。
拓銀の破綻が地域経済の崩壊まで進む事態になり、巨額な公的資金を注入してまでも銀行救済に本腰を入れようとした。これでは道民はもとより旧拓銀行員も、一体なんのために振り回されてきたのかと思うと腹立たしい限りである。
国策企業の性質で考えるならば拓銀は残すべきであった。課長以上の全員に責任を取らせてでも、北海道と言う「地域」のためには拓銀は残すべきだった。これは旧自治省の業務懈怠が残した産物ではないだろうか。
参考文献:拓銀はなぜ消滅したのか(北海道新聞社編)、北海道新聞、朝日新聞。