5 悪辣な対日石油禁輸
① 事前に練られた準備
米国を主役とした米英蘭の対日石油嫌がらせと圧迫は、人類の歴史にかってみられないほど辛辣な、しかも水も漏らさぬ用意周到なものであった。しかも時々刻々の情勢に対して極めて敏感に、これでもかこれでもかと首を締めておいて心臓の弱っていくのを冷静に計算しつつ、到底我慢しきれないで立ち上がりはしまいかと絶えず顔色を窺っていた
対日石油嫌がらせと圧迫は、意地悪い執拗な屈服策戦であった。日本はそれ故に危うく窒息せんとしたほど、強大かつ深刻な効果を持った経済戦術であった。石油が近代国家に不可欠な重要性を保つために、石油の入手困難は一国の国防力、戦闘力を徹底的に骨抜きにしてしまうのみか、一国の存在そのものをも脅かすものであることは今日もはや説明する必要はないだろう。
米国があえて対日石油対日石油嫌がらせと圧迫を企画してそれにより日本の屈服を予期した事、日本もそれに対して生か死かの一大戦争に、国家としての生きる道を見出さざるを得なかったことを我々はぜひ知らなければならない。そこで前提知識として極めて簡単に説明しておこう。
大東亜戦争の勃発前の状態においては、第二次欧州大戦勃発後といえども石油は世界的にみて著しく生産過剰であった。産油国は産油を制限するために大きな犠牲を払っていたばかりか、将来の生産力においても著しく過剰を示していた。
しかも最も皮肉な現象として米ソ両国を除いては比較的文化の程度が低く石油をあまり消費せず、一朝有事の際にもあまり石油を使用しないような国々に多く産出し、石油消費国だある世界の強国にはあまり恵まれていなかった。
例えば昭和15年の供給に基いて計算すると、世界第三の産油国であるヴェネヅェラはその産額の95%に達する輸出能力を持ち、イランは85%、蘭領東印度は71%、ルーマニヤ68%、メキシコ53%、コロンビアは84%という輸出能力を持っていた。
トップへ戻る
これに対して、世界の強国はその石油消費の大部分を輸入、あるいは代用燃料、人造石油、その他に依存しなければならない。しかもその依存率は、同年度においてイギリス本土がほとんど全部、ドイツが87%、フランスが98%、イタリヤが84%に達し、程度の差こそあれ日本もしかりであった。
米英は、世界各国において石油業を自ら営むことにより資源的的生産的に世界の石油を掌握し、油槽船、輸槽車、送油管線、石油運搬車、船油所を七つの海と五大陸に配置することにより石油の通商と配給をも支配し、また技術的にも世界を支配していた。
米英は石油なき国あるいは石油を持ちながら自国の石油業を持たぬ国、ヴェネヅェラ、イラン、蘭印、ルーマニヤ、メキシコ、コロンビア、その他に対して高価に石油を売りつけ、優良品を豊富に供給して米英に対する依存性を完全にする方策に出ていた。
米英はもと日本を石油の利益市場とみていたが、日本には貧弱ながらも国内石油業が存在し、これを壊滅させることは日本が許しそうもなかった。日本はその国力の伸展に従い石油の自給自足、石油における国家の自立性を確立する決意を表明していることを知ると一転して骨抜き作戦にでた。
優秀石油製品を安価に供給し、競争相手の日本の石油会社に対して世界でも稀にみる良質原油を低価で供給し、装置、機械、特許を譲渡し、要求があれば技師及び職工すらも派遣し、一切の資材を持参して装置の建設にもあたってくれた。
その結果、石油のあらゆる分野において自らの技術を持つ必要がなくなった。ただ外国の本を読み、外国へ注文し、あるいは見に行って買って帰った技術や機械を運転し、真似するだけの技師だけとなり、輸出港にいる品質証明書の証明が正しいかどうかを検査する試験所があれば足りた。
このような状態は、必然的に石油における国家の自立権を喪失させる結果を招来するので、昭和9年7月から我が国の統制法規の先駆をなす石油業法が実施されたが、時すでに遅しであった。
トップへ戻る
米国が対日石油嫌がらせと圧迫を行うにあたって調査したのは、日本に対する包囲が完全であるか、抜け道を通る石油が日本を救いはしましか、ということであった。これには二つあった。
第一は、日本が平和的に第三国を利用するのではないかということある。これに対して日本の陣営にある国が石油を供給しようとすると、その国の絶対的必要量を考慮して石油の供給を停止し、対日石油通過貿易を不可能にする措置を講じた。
第二は、日本が非常手段に訴えて第三国の石油在庫占領に備え、日本が急襲する恐れのある第三国の石油在庫を刻々最低限に止め、国際情勢が緊迫するや供給そのものを停止した。
このようにあらゆる点から考慮し、石油入手不可により日本を軍事的産業的に半身不随に陥らせて屈服させ、万一決然と立つに至っても時すでに遅く、国力弱体化してたちまち降伏さざるを得ないようになし得るとの確信をもって、日本の首を締めにかかったのである。
トップへ戻る
② 巧妙辛辣な術策
昭和12年7月に支那事変が勃発すると米国の感情的世論は極度に興奮し、政府に対して全面的対日石油禁輸を迫る声が大きくなってきた。これは、イタリアのエチオピア遠征当時の米国民の興奮と同じようなもので、時を経るにつれて鎮静化し全面的対日石油禁輸が何を意味し、いかなる事態を招くことになるか検討し始め、新聞雑誌はこれに関する専門家及び研究家の意見を掲げた。
日本に石油を全面敵禁輸するならば、日本は支那事変を即座にやめなければならない。長期にわたって全面的禁輸を持続するならば、日本はその存在も危うくするであろう。したがって、日本は生存上どうしても南方の石油を奪取するだろう。そこで似て米国との戦争は不可避となる。
その場合、ソヴェトは敵か味方か分からない。米国は将来を問わず現在は絶対に戦う単位ではないというものであった。この当時遺憾なのは、日本の貿易業者やアメリカ通と言われる人々が、もっともらしいその実きわめて愚劣で認識不足な理由を述べて、米国の対日石油禁輸不可能論を唱え、日本の世論を支配して各方面に悪影響を与えたことである。
ルーズベルト大統領は、「現在米国は軍事的に無力である。しかし、いまに米国の再軍備は進捗し戦いには必ず勝つ。その時には対日石油禁輸を強行して日本を屈従させる。だからそれまでは、そんな素振りを少しも見せずに油断させておかなければならない」と演説している。
このような狡猾な態度に出て、これがまた日本のアメリカ通及び貿易業者に一層の自惚れを与えたのだった。(その間の消息及び米国の作戦の成功については、後日、米国自らが暴露し自慢したものであった。)
トップへ戻る
③ 輸出許可性
7月15日にビットマン上院外交委員長が議会へ提出した提案は、九ヶ国条約に違反して米国民の生命を危うくし、あるいは米国区民の権益を侵害した国に対し、武器弾薬は勿論のこと、石油やくず鉄を売ることを禁止せよと言うのが趣旨だった。
だが、日米通商条約的には、条約国の一方は他の諸国に対して一律にある物資を輸出禁止にするのでない限り差別的に相手方へ輸出禁止をしてはならないと規定しているので、ビットマン案は明らかにそれに抵触する。
ハル国務長官及びルーズヴェルトは、法律専門家にも諮問すると彼らの回答も当然抵触するというものであったから、その真偽を一時中止して六か月の猶予をもって条約の破棄を通告してきたのであった。
これは米英心酔者や米国通にとって、米国は決して対日石油う禁輸に出ないと主張していた一部の貿易業者にとってはまさに青天の霹靂だった。と同時に、戦争の危機切迫と相まって航空揮発油の対策をどうするかということであった。
昭和14年12月20日、当時フインランドの一般市民に対する空爆でソヴィエトに対し、米国は航空揮発油の製造装置、技術特許権、技術情報に対する彼らの「道義的禁輸」を実行した。
その後、昭和15年1月26日にいよいよ無条約状態に入ると、米国は日本の周囲から遠まわしに首を絞めることに主力を注いだ。5月28日、ルーズヴェルトは第二次大戦の経緯に鑑み、急速に国防を充実するとして国防諮問委員会をつくり、財界有力者7名を委員とした。
トップへ戻る
大統領が同委員会へ諮問した結果、議会に提出した国防強化促進法は圧倒的な世論の支持を得た。7月3日、許可制に入るべき品目が発表され5日かが実行された。
この当時、英国が一切の中立国油槽船を引き寄せてしまい、日本が石油の在庫を増やすために輸入しようとすれば、パナマ国籍の油槽船を使用するのが最も有効な方策の一つであった。
6月27日にルーズヴェルトは、アメリカ領海におけるすべての船舶の運航及び碇泊を統制するため、日本向けの石油運搬に米国油槽船の使用を禁じ、パナマ国籍の油槽船にまでも及んだ。
6月25日に許可制品目に簡単な行政命令で、石油及び石油製品と屑鉄及び屑部金属が追加された。新聞が禁輸と報道したことに後日説明を発表するとる約束したが、7月23日に大統領が発表した布告及び規則に、問題にされた行政命令には何ら言及していなかった。
関税調査官への通達では、上等な航空揮発油、同原料油、航空揮発油の性能を向上せしめる添加物並びに上等な航空潤滑油も輸出許可制下に置くとされていた。さらに、輸出許可申請書には第三国を経由して日本へ輸出されるのを防止する事ができるようになっていた。
トップへ戻る
④ 禁輸の手段と経路
昭和15年8月1日に、米国は航空揮発油の西半球以外への輸出を禁止し、その日から対日石油禁輸は日を追うにつれて徹底的となった。それは日を追うごとに段階別に実施された。
第一段階 日本に最優秀な航空揮発油を輸出しない。
第二段階 日本に最優秀な航空揮発油及び潤滑油を輸出せず、最優秀航空揮発油の原
料油と航空揮発油の性能を向上させる添加剤も輸出しない。
第三段階 石油製品の精製技術及び装置が米国の水準に近づくのを妨げる。
第四段階 日本には少量の国内産油があるので、それが増大しないように妨げる。
第五段階 日本の石油貯蔵を増大させず、かえってそれを減少させるように巧妙な内
面的策略を設ける
これにより、英国石油会社のライジング・サン社は、突如として平和的なもっともらしい理由により販売用石油の補給が不可能となったとを告げて供給を止め、米社スタンダードヴァキウム社も、突如として他の理由から販売量を短期間辞退するとした。
米国国務省管理局の発行する輸出許可証は同局が警告なしに無効とでき、1年以内に輸出港をでる期間は15日に短縮された。許可を受けたとの電報を受け取ってから横浜港を出ても間に合わないため、途中まで出向いていなければならない。
トップへ戻る
しかし、いつ許可証が発行されるか分からずに米国へ走り、米国へ着いたころに不許可になれば、油槽船は再び自らの燃料を消費して引き返さざるを得ないことになった。
第六段階 日本が入手できる量は米英を合算して数字を抑え、その石油の品質を低下
させた。
第七段階 最後に一滴も石油を日本の手に入らないようにした。
米国の対日石油嫌がらせと圧迫はこのような順序で、いかに思慮遠慮でありいかに巧妙な計画的で一歩一歩日本の首を絞めていったものであり、これが戦争に突入した原因であることは感得されるであろう。
かくして、支那事変の勃発当時、米国世論が無責任にも高唱した対日石油全面禁輸、すなわち一滴の石油も日本に渡さないという声は、昭和16年7月26日の日本資産凍結令の公布実施によって実現された。
トップへ戻る
⑤ ルーズヴェルトの石油演説
在米日本資産凍結令は石油にのみ関するものではないが、石油が最大の原因であったことはルーズヴェルト大統領の有名な石油演説によっても明らかである。すなわち昭和16年7月末、日本と佛印との共同防衛交渉が進捗する気勢を見て、米国の新聞および世論は極度に悪化したが、ルーズヴェルトはこの世論を抑えることなく、しかもかえって対日石油嫌がらせと圧迫を極度に徹底させて、それによって戦争が南太平洋により米国もなお戦果を交えるも辞さない態度を明らかにした。
これを最も露骨に物語ったものは昭和16年7月24日、国防参加有志委員会の会員に対して、ルーズヴェルトが行った演説である。この演説で大統領は「対日妥協施策を打ち切る」と題して掲載した米国新聞もあったくらいで、石油に託した宣戦布告であったと共に最後の恫喝でもあったのだが、その恫喝も声なきを見るやたちまちにして在米日本資産凍結令を公布実施したのである。その石油演説で彼はこう言っている。
「(前略)ここすなわち大西洋岸において諸君は、内務卿イックスが石油管理官として東海岸において十分な石油がないという問題に直面していること。彼が何人に対しても各人の揮発油消費量を削除すべきことを熱心に要求していることを新聞で読まれたであろう。
さて、私はニューヨークのハイド・パークに住んでいるが、『数千トンの揮発油が西海岸のロサンジェルスから日本に向けた出されており、我々は侵略行為のように思えることを、日本のために助けているわけだと新聞で読んでいる。その同じ時に、何故揮発油を節約することを要求されるのであろうか』といい得ないだろうか。然り、答えは非常に簡単である。世界戦争は現在行われており約二ヶ年も行われてきた。
戦争のごく当初からのわれわれの努力の一つは、戦争が勃発していない地域に世界戦争が波及するのを防止しようということであった。そして、これらの場所の一つは太平洋と言われる地域、地球上の最大地域の一つである。
トップへ戻る
その南太平洋には、蘭印、海峡植民地及び印度支那のごとき、ゴム、錫、その他いろいろの物をわれわれがそこから得なければならない場所が存在するのである。更に、オーストラリヤの肉、小麦及び穀物の余剰をイギリスの手に入るように助けなければならない。
だから、南太平洋に戦争が勃発するのを防止することは、我々の利己的な国防見地から見て非常に緊要であった。(中略)ところが、ここに日本と呼ぶ国がある。彼らがその帝国を南方に拡大する侵略的意図を持っていたかどうかはともかくとして、彼らは北にあって彼ら自身の石油をもっていなかった。
そこでもしわれわれが石油を切断してしまったら、彼らは今から一年前にたぶん石油を求めて蘭印へ行ったであろうし、そうすれば諸君は戦争に入っていたであろう。そこで『ある希望をもって、石油を日本に行かせている手段』と諸君が呼んでもいい手段が、われわれ自身の利益のためにイギリスの防衛および海洋の自由の利益のために、南太平洋を今まで二ヶ年間も戦争の域外に保たせるように働いてきたのである。」
以上をもって米国の対日石油石油嫌がらせと圧迫蛾がいかに徹底的であったかは容易に了解されると思うが、石油を輸出許可制中に編入するに際しても、いかに包括的石油、石油と名がつき石油に関係すればどんなものをも、一つの手抜かりもなく網羅しているかのが昭和16年8月2日に実施された全石油の輸出規格表である。
トップへ戻る
⑥ 日蘭会商の悪辣な逆用
対日石油嫌がらせと圧迫作戦として、あくまでも現実主義者であると共に、残忍極まりない彼等はさらに尽くし得るすべての手を打ち、機会のすべて手を利用することを忘れなかった。それには、
① 日本が平和的にあるいは武力的に入手するかもしれない第三国に於ける石油在庫を
極度に低下させておくこと。
② 日本周辺国の石油による操縦
③ 石油関係者の日満支におけるスパイ行為
④ 英ソ蒋に対する積極的な石油援助(但しソヴェトに対して微妙なる米ソ関係に伴っ
て、あるいは嫌がらせあるいは圧迫を緩和し、あるいは積極的に援助した。)
その最も悪質な態度をものがたる一例は日蘭会商の逆用だ。日蘭会商の内容は今なお秘密とされており、我々はこれを知る由もないが、昭和16年12月13日の日刊紙は「英米に踊らされ石油協定も破棄、日蘭経済交渉の経緯」と題して次の一文を掲げた。
「第二次欧州大戦を機会として、久しき間世界経済の基底となっていた自由通商主義は根底から葬られ、列国、特に世界新秩序を目指す枢軸国家は、自給自足経済主義を強く提唱し、我が国も大東亜共栄圏理論を力強く展開するに至った。
昭和15年9月日本はこの大東亜共栄圏なる広域自給自足経済圏確立の意図に基づき、蘭領東印度政庁といわゆる日蘭経済会商を開催することに意見一致し、同月12日木林昇降大臣は現職のまま蘭印に乗り込み、同月16日には蘭印首都バタヴィヤにおいて日蘭会商第一次基礎会議が開催され、本邦側は戦時重要資源たる買油交渉を開始した。
その後の日独伊三国同盟の締結ののち、日蘭両国関係は外交的にも経済的にも極めてデリケートな関係に立った中にあって、小林特使は年130万トン(このほか15年には約70万トンの買油契約あり)の買油交渉に成功し、10月17日には日蘭会商進捗状況に関する共同コミュニケの発表をなし得る段取りまでこぎつけたわけである。
トップへ戻る
しかし、この買油交渉内容は当初われの蘭印に提出した要求額に比較すれば、実にその半分にしか充たないものであった。これによってみても、蘭印側はわが東亜共栄圏の理念を解せず、もっぱら米英依存政策にでたことは明らかである。特に買油交渉も蘭印政庁は材蘭印米英系石油会社との交渉の斡旋的役割を示したにすぎず、交渉は全部米英政府の指示に基づき行われたものであることは特に注意すべきであろう。
こんなわけで、その後の蘭印政庁の日本に対する経済的政策は、米英の悪辣なる手段よって封鎖的色彩を農くし、11月9日には満支その他ゴム、錫の輸出を制限するの挙に出た。しかし、我が国はあくまで両蘭印の経済的定型を緊密化する意図のもと、同年11月30日には芳澤特使を蘭印に特使し、日蘭経済交渉に当たらしめることになり、同氏は同年末蘭印に到着した。
その後、小林特使が当時すでに下準備の成立した日蘭印銀行間の金融協定の調印が12月24日に行われたが、芳澤特使が乗り込んで以来蘭印政庁の日本に対する敵意は次第に表明に現れるようになり、15年2月1日遂に蘭印政庁は調印の東洋新秩序編入に反対の旨を日本政府に申し入れ、5月5日には為替管理法を強化するなど、日蘭交渉はもはや前途打開の道なき事態に立ち至ったので、政府は日蘭会商を6月17日に打ち切り両国の通商関係不変を声明した。
その後日蘭関係は外交的にも経済的にも最早友好国としての関係は薄くなっていたところ、7月26日米英両国の対日資産凍結令の発動と呼応して、同月28日在蘭印試算を凍結すると同時に、日蘭石油協定および経済金融協定を停止するとの挙にでた。
米英両国は総合的見地から「日本を怒らせないでおくために供給しなければならない石油の絶対量」を決定しておき、その一部を蘭印からの供給量へ回した 。しかも間極めて悪質な術策を弄して、実質的に日本をして失うところのみで得るところのないように仕向けたのである。
トップへ戻る
すなわち、合衆国政府は対日石油嫌がらせと圧迫を行うにあたって最大関心事は、日本が蘭印の石油を奪取しはしまいかということであった。かれらはまず合衆国からの石油供給の停止が近いのをにおわせながらも、日本がその準備対策として合衆国からの購入石油の一部を蘭印に振り返ることを黙視するばかりかかえって大いに歓迎した。
この場合も狡猾な彼らは、蘭印石油中上質なものは日本に供給させないようにすることを忘れなかった。更に距離の接近により運搬費の軽減分だけを蘭印石油の売値に付加し、アメリカ石油を蘭印石油に乗り換えても日本は何ら益するところがないようにさせた。
そして、日本が得るところはアメリカ石油から蘭印石油へと品質低下による損失のみとさせた。このように悪辣無動な最多の術策に禍されて、日蘭会商そのものは予定の成功を収めることができなかったが、
① 蘭印には蘭印の石油業はなく、あるものは米英の石油業のみであること。
② 蘭印政府は米英石油業者に対して全然無力であること。
③ 蘭印にある米英石油会社は世界を独占する二大石油トラストの一部であり、米英の
国家と石油会社は一体であること。
④ 蘭印緒石油問題を決定する権限は、ロンドンでありワシントンであること。
等々動かすことのできない明確な形において、日本人の覚醒と覚悟を促した。
トップへ戻る
⑦ 彼等の期待した窒息
このようにして昭和17年7月26日以後、日本には一滴の石油も入ってこず、第三国を通して輸入することもできなくなった。このような状態のときに、米国のノックス海軍長官は次のように言明した。
「日本は大戦において1年や1年半位徹底的な戦時消費をやっても困らぬだけの石油、ガソリンの予備貯蔵を持っているという印象を受ける。」
トップへ戻る

 を知られたくない占領軍は真っ先に「米英挑戦の真相」の焚書を実施した。この本の刊行趣旨で、大東亜戦争調査会の有田八郎氏は次のように述べている。
を知られたくない占領軍は真っ先に「米英挑戦の真相」の焚書を実施した。この本の刊行趣旨で、大東亜戦争調査会の有田八郎氏は次のように述べている。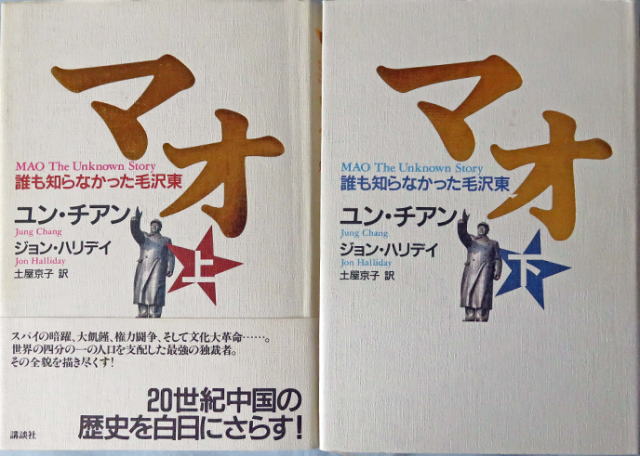
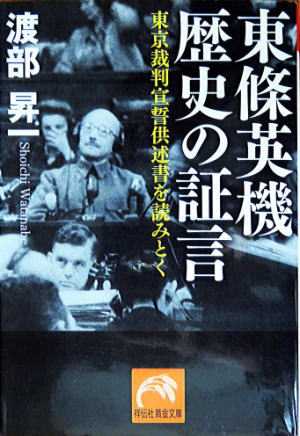 れた清瀬一郎博士とアメリカ人弁護士ブルーエットの両氏が九ヶ月にわたり内容の事実確認を行ったものであるが、大東亜戦争を考察する際に取り上げられたことはない。
れた清瀬一郎博士とアメリカ人弁護士ブルーエットの両氏が九ヶ月にわたり内容の事実確認を行ったものであるが、大東亜戦争を考察する際に取り上げられたことはない。